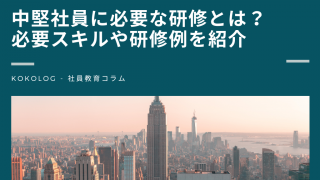セキュリティ・コンプライアンス意識が向上!社内で広がる声かけの輪

求人広告を使った採用集客手法から、応募受付代行やシステム導入提案などの歩留まり改善提案まで行う株式会社ティーオーエイチ様。
場所や業種、企業ごとのフェーズなど、異なる状況に合わせた人材支援を展開し、各社に合わせた独自のソリューションを提供している。
また、社会的なIT化の加速に伴い、エンジニアをはじめとしたIT需要の高まりに応じたサービス提供も進めている。
今回は株式会社ティーオーエイチ様に、kokoroeを導入して得られた効果や率直な感想を伺った。
導入の背景「教える側も、教えられる側も感じるストレス」
「kokoroe」導入前の研修内容
松本:
これまでは、会社全体で行う研修は年に1回程度、情報セキュリティやコンプライアンスについて座学を行う程度でした。教育はOJTが中心で、都度先輩社員が教えるというスタイルです。業界知識などは、反復して学ぶことで定着できるようにしたいという考えのもと、上司など役職者がメンバーとコミュニケーションをとりながらこまめにリマインドをかけていくという形で行っていました。

「kokoroe」導入の背景
松本:
まず、社歴を問わずコンプライアンスやセキュリティ面に関する意識を向上させたかったというのがあります。また、上司やメンバーに都度リマインドをかけて復習を促すというやり方は、言う側・言われる側ともにストレスを感じさせてしまうこともあって…。
北野:
上司は同じことを何度もメンバーに繰り返し伝える必要があり、「何回も伝えているのにどうして覚えてくれないんだろう?」と感じたり、時間的な工数が取られてしまうという事象が発生していました。一方で、言われる側のメンバーも、都度上司から指摘されるということに少なからず負担を感じることもあり、どちらにとっても大なり小なり負担があるという状況になってしまっていたと感じています。
松本:
kokoroeのお話を聞いた時、「反復して学ぶことで知識を定着させる」というコンセプトが私たちのやりたいことと一致しているなと感じました。また、1日5分程度のテストなので、毎日受講でも受講者の負担が少ないことも良かったです。やりたいことをシステム的にできるというのは魅力でした。
導入後の効果「メンバー間の声かけで芽生え始めた意識」
「kokoroe」導入後の変化
松本:
本格的に導入し始めて約1ヶ月程度なので、まだ実感しきれていない面も正直ありますが、当社の雰囲気としてコミュニケーションが取りやすく社員間の会話も多いため、実際に会話の中でkokoroeの話題がでることがありました。
北野:
例えば、「今日こんな問題がでた」「この問題を間違えた」といった会話があったり、誰かが間違えた問題を別の誰かが解説してあげたりといったこともあります。出題した問題について「知らない内容もあり、学びになりました」という声もありました。

松本:
また、「離席をする時にPC画面をロックをする」という問題を出した後には、実際に離席をする時にメンバー間で「(PCの)ロック掛けた?」などの声かけも発生するようになり、まだ一部かもしれませんが、少しずつ意識が高まり始めていると感じています。
北野:
kokoroeの利用について、セキュリティ意識の向上には本当に効果的だなと思います。今お話しした離席時の画面ロックも、当たり前といえば当たり前のことで、問題自体はOKかNGかを答えればいいだけの簡単なものでも、自分の判断でNGな行為だと回答したことに対して責任を持つようになるんです。改めて気をつけなきゃ、という意識を持ってくれるイメージですね。また、知らなかったとしても結果画面できちんと解説を読んでもらっているので、意識向上もできるし、理解度を深めるということもできます。
今後の活用方法・期待すること「受講の習慣化と意識の拡充」
「kokoroe」の今後の活用方法
松本:
まだ受講が習慣化できていないメンバーもいるので、まずはそこを徹底したいですね。システムの通知としてリマインドメールで毎日受講を促してくれていますが、見ても受講し忘れてしまう人もいるので、今は私が受講者に直接声かけをするようにしています。ここはシステム上で通知の頻度を増やしたり、時間や曜日指定ができるようになると嬉しいですね。

北野:
当社は大きく分けて求人広告部門とIT人材派遣部門の2つの事業を行っていますが、現在kokoroeを受講しているのは求人部門のみに絞っているため、今後はIT部門でも問題を作成して受講させたいと考えています。
松本:
他にも、入社間もないメンバーに業務知識を学んでもらったり、営業なら営業、制作なら制作のように部署ごとの理解度を測るツールとしても活用していきたいです。機能的な改善は今後も進められていくとのことでしたので、そちらにも期待しつつ、当社としてももっと幅広い場面で活用できるようにしていきたいですね。