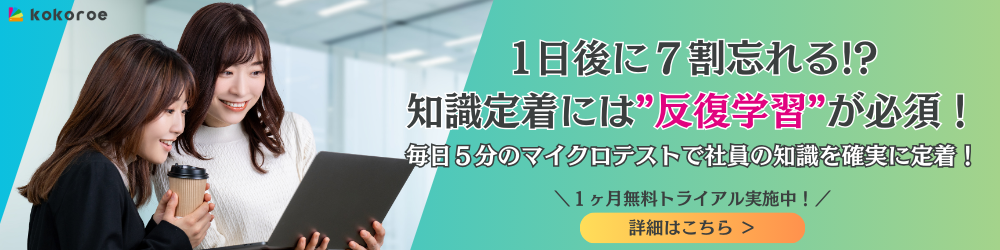リスクマネジメントとは?人事担当者が知っておくべき基本と実践法を解説!
リスクマネジメントは、企業の持続的成長と信頼を守るために欠かせない取り組みです。特に人事・教育担当者は、社員のリスク意識を高め、組織全体のリスクを未然に防ぐ重要な役割を担っています。本記事では、リスクマネジメントの基本から実践方法、効果的な社員教育、社内体制の整備までをわかりやすく解説します。
1: リスクマネジメントとは何か?その基本を理解しよう

企業経営において避けて通れないのが「リスク」です。
法令違反、情報漏洩、自然災害、ハラスメントなど、あらゆるリスクが企業の信用や業績を脅かす可能性を秘めています。こうしたリスクに対処し、損失を最小限に抑えるための仕組みが「リスクマネジメント」です。
特に人事部門や教育担当者にとっては、社員のリスク感度を高め、問題の未然防止を図ることが重要な役割となります。この章では、リスクマネジメントの基本的な定義と目的、そして企業がいま取り組むべき理由、人事部門の具体的な関わりについて解説します。
1-1: リスクマネジメントの定義と目的
リスクマネジメントとは、「企業活動におけるあらゆるリスクを特定・評価し、適切にコントロールすることで、損害の発生を未然に防ぎ、企業価値を維持・向上させる一連のプロセス」です。
具体的には以下のような目的があります:
- リスクの“見える化”によって予防策を講じる
- 万が一のリスク発生時に迅速かつ的確に対応する体制を整える
- 社員一人ひとりのリスク意識を高め、組織全体の危機対応力を強化する
- 信頼性の高い企業ブランドを構築・維持する
単にリスクを「回避」するだけでなく、組織の“守り”と“攻め”の両面で機能するのが、現代のリスクマネジメントの特長です。
1-2: なぜ今、企業にリスクマネジメントが必要なのか
現代の企業環境は、従来よりも複雑かつ不確実性が高まっています。以下のような背景から、リスクマネジメントの重要性はかつてないほど高まっています。
● コンプライアンスへの社会的要求の高まり
SNSなどで情報拡散が瞬時に起こる現代において、一度の不祥事やトラブルが企業の信用を大きく損なう可能性があります。法令遵守や社会的責任を果たすためには、日常的なリスク管理が不可欠です。
● 労務・人材に関するリスクの多様化
ハラスメント、メンタルヘルス問題、リモートワーク下での労務管理の難しさなど、人的リスクが企業の根幹を揺るがすケースが増えています。
● デジタル化による新たな脅威
情報セキュリティやサイバー攻撃など、ITリスクも無視できません。特に人事データや個人情報を扱う部門では慎重な対応が求められます。
このように、企業が持続的に成長していくためには、もはやリスクマネジメントを“選択肢”ではなく“経営の基盤”として捉える必要があります。
1-3: 人事部門が担うリスクマネジメントの役割とは
人事部門は、「人」に関わるリスクの最前線に立つ重要なポジションです。以下のような役割が求められます。
● 社員のリスク意識を育てる教育・研修の設計
ハラスメント防止、情報セキュリティ、コンプライアンスなど、リスクを“自分ごと”として捉えさせる教育の導入は、人事・教育担当者の大きなミッションです。
● 組織風土の整備と心理的安全性の確保
社員がリスクを早期に報告・相談できる環境づくりも、リスクマネジメントの一環です。これは心理的安全性を高める施策と密接に関わります。
● 人事制度や評価制度との連動
リスクに対する適切な行動が評価されるよう、評価制度や行動指針にリスクマネジメントの視点を反映させることも有効です。
人事部門がリスクマネジメントに積極的に関わることで、組織全体の危機耐性が強化され、社員の信頼と安心感も向上します。
次のセクションでは、実際に企業で想定されるリスクの種類と、その具体的な事例について詳しく見ていきましょう。
2: 企業で起こり得るリスクの種類と具体例

リスクマネジメントを実践するには、まず「どのようなリスクが自社に存在するか」を明確に把握することが第一歩です。
企業活動におけるリスクは多岐にわたり、その内容によって対処法や教育のあり方も変わってきます。
この章では、人事部門が特に注目すべき「人的リスク」「ITリスク」「外的リスク」の3つに分けて、それぞれの具体例と対応の視点を解説します。
2-1: コンプライアンス違反・ハラスメントなどの人的リスク
人的リスクとは、従業員の行動や人間関係、労務管理に関連して発生するリスクです。
人事・教育担当者が最も関与する領域であり、放置すれば組織の信頼や職場環境に深刻なダメージを与える可能性があります。
● コンプライアンス違反
たとえば、労働基準法違反(過重労働、未払い残業など)や不適切な採用活動、個人情報の取り扱いミスなどが該当します。
法令を正しく理解していないことが原因になるケースが多いため、社内ルールの明文化と定期的な研修が不可欠です。
● ハラスメント問題
パワハラ、セクハラ、マタハラなどのハラスメントは、社内での相談が遅れれば重大な訴訟や離職につながるリスクがあります。
防止には、相談窓口の設置やeラーニングによる啓発、管理職への対応教育が効果的です。
● モラルや行動規範の逸脱
SNSの不適切利用、社内外での迷惑行為、誠実性を欠いた振る舞いなども人的リスクの一つです。
企業理念や行動規範の共有・浸透が求められます。
2-2: 情報漏洩やシステム障害などのITリスク
近年、リスクマネジメントの中でも特に注目されているのがITリスクです。
デジタル化・クラウド化が進む一方で、情報セキュリティやシステムの脆弱性が新たなリスクとして浮上しています。
● 情報漏洩
人事が扱う社員情報、評価データ、健康情報などはすべて機密性が高く、万が一漏洩すれば社会的信用を大きく損ないます。
USBメモリの持ち出しや誤送信といったヒューマンエラーによる漏洩が多いため、社員教育によるリスク意識の向上が有効です。
● サイバー攻撃・ウイルス感染
外部からの不正アクセスやマルウェア感染も大きなリスクです。
セキュリティソフトの導入やシステムの定期更新に加え、従業員のITリテラシー向上が不可欠です。
● システム障害・データ消失
基幹システムの停止やバックアップミスにより、業務が一時的に麻痺することもあります。
クラウドサービスの利用やBCP(事業継続計画)の策定がリスク軽減に寄与します。
2-3: 災害・パンデミックなどの外的リスクとその影響
企業のコントロールを超える外的要因も、リスクマネジメントにおいて無視できない要素です。
自然災害やパンデミックは業務停止・収益減少だけでなく、社員の命や健康にも関わる深刻な影響を及ぼします。
● 自然災害(地震・台風・豪雨など)
突然の災害に備えた避難マニュアルや安否確認体制の整備は、人事部門の重要な責任です。
また、リモートワークの環境を整えることで、事業継続への柔軟な対応も可能になります。
● パンデミック(感染症の流行)
新型コロナウイルスをはじめとした感染症リスクは、従業員の健康管理と働き方の見直しを促しました。
検温や体調申告の仕組み、在宅勤務制度の導入などがリスク対策として重要です。
● 社会的・経済的変動
急激な為替変動、物価上昇、国際情勢の悪化なども、間接的に人事施策に影響を及ぼすリスクです。
人材確保や賃金制度、採用戦略の柔軟な見直しが求められます。
このように、企業を取り巻くリスクは多種多様であり、予測不能な事態も少なくありません。
人事や教育の現場でも、あらゆるリスクを視野に入れた「備え」が欠かせません。
次章では、これらのリスクにどう対応すべきか、人事・教育担当者が担うべきリスクマネジメントの具体的なステップについて解説していきます。
3: 人事・教育担当者が行うべきリスクマネジメントのステップ

リスクマネジメントは、単に危機を回避するだけでなく、企業の持続的成長を支える重要な経営活動の一つです。
特に人事・教育部門は、組織内のリスクをいち早く察知し、社員への教育や制度整備を通じて、リスクの発生を未然に防ぐ役割を担います。
この章では、実際に人事・教育担当者が取り組むべきリスクマネジメントの基本ステップを、「リスクアセスメント」「対策の立案・実行」「PDCAによる改善」に分けて解説します。
3-1: リスクの洗い出しと評価(リスクアセスメント)
リスクマネジメントの第一歩は、「どのようなリスクが存在しているか」を把握することです。
このプロセスを**リスクアセスメント(リスク評価)**と呼び、以下のような手順で行います。
● リスクの洗い出し
社内で起こりうるリスクを、部署ごと・業務ごとに幅広くリストアップします。
例:ハラスメント、情報漏洩、人材流出、評価の不公平、採用トラブル など
ブレインストーミングや過去の事例、外部データを活用すると効果的です。
● リスクの評価(重要度と発生確率)
洗い出したリスクを、「発生頻度」と「影響度(被害の大きさ)」の2軸で分類・可視化します。
たとえば、以下のようなマトリクスに整理すると、優先的に対応すべきリスクが明確になります。
| 発生確率 ↓ / 影響度 → | 小 | 中 | 大 |
| 高 | 優先的に対処 | 早期に検討すべき | 緊急対応対象 |
| 中 | モニタリング対象 | 対策を準備 | 優先的に対処 |
| 低 | 無視も検討可 | 情報収集を継続 | 注意喚起が必要 |
この段階で、「何を優先して対策すべきか」が判断できるようになります。
3-2: リスク対策の立案と実行
次に、リスクアセスメントで特定・優先順位付けされたリスクに対して、具体的な対策を計画し、実行していきます。
● 対策の種類を検討する
リスクへの対応方法は主に以下の4つに分類されます。
- 回避(Avoid):該当リスクを完全に回避する(例:危険な業務プロセスの廃止)
- 軽減(Reduce):発生確率や影響度を下げる(例:ハラスメント防止研修の実施)
- 移転(Transfer):他者にリスクを移す(例:保険の加入や外部委託)
- 受容(Accept):コストや重要度から許容する(例:軽微なクレームの容認)
人事や教育の現場では、「軽減」が最も多く活用される対策です。
● 実行に向けた社内体制づくり
対策を実行に移すには、以下の要素が重要です:
- 対策内容と責任者を明確にする
- 社員への周知・研修を行う
- 実施スケジュールとKPIを設定する
対策の実行には「属人的な対応」に頼らず、制度として社内に組み込むことが求められます。
3-3: リスク対応後の評価と改善(PDCAサイクル)
対策を講じた後は、「それが有効だったかどうか」を評価し、継続的に改善することが重要です。
ここで活用されるのが、**PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)**です。
● Plan(計画)
リスクごとに対応方針を決め、対策のKPIや評価基準を設計します。
● Do(実行)
実際に教育施策や制度を導入し、社員の行動変化やリスク件数を観察します。
● Check(評価)
実施後に、目標の達成度やリスク軽減の効果をデータやアンケートで検証します。
● Act(改善)
うまくいった施策は継続し、効果が薄いものは改善や再設計を行います。
このサイクルを繰り返すことで、企業のリスク耐性は段階的に強化されていきます。
人事・教育担当者がリスクマネジメントにおいて果たすべき役割は、計画的かつ継続的な取り組みによって、組織の安心・安全を守ることです。
次章では、こうした取り組みをさらに強化するための「社員教育」の進め方について、具体的に解説していきます。
4: リスクマネジメントを強化する社員教育の進め方

リスクマネジメントを社内に浸透させるには、**社員一人ひとりの「リスクに対する意識」と「正しい行動習慣」**を育てることが不可欠です。その中核を担うのが、教育・研修の取り組みです。
人事・教育担当者としては、「ただ教える」だけではなく、社員の行動変容につながる研修をどのように設計し、どのような方法で実施するかが重要なポイントになります。
この章では、リスクマネジメントを強化するための社員教育の進め方について、具体的な設計のポイントから実践手法までを詳しく解説します。
4-1: 社員のリスク意識を高める研修設計のポイント
リスクマネジメント研修を設計する際には、単なる知識の伝達ではなく、**「リスクを自分ごととして捉える意識改革」**を目的に据えることが重要です。
● リアルな事例を使って“危機感”を醸成
実際の企業トラブルや社会問題をもとにしたケーススタディを導入することで、社員の関心と臨場感を高めることができます。自社の業務に近い事例を選ぶと、より実践的な気づきが得られます。
● 行動指針や価値観と結びつける
企業理念や行動規範とリスクマネジメントを紐づけることで、「なぜ自分たちが守るべきなのか」を明確にし、日常的な行動に落とし込みやすくなります。
● 双方向型・体験型の研修スタイル
座学だけでなく、ディスカッションやロールプレイを取り入れることで、参加者の理解度と定着率が向上します。心理的安全性を確保し、意見を出しやすい場づくりも大切です。
4-2: 階層別・職種別に行うべき教育内容の例
リスクマネジメント教育は、「一律」で行うのではなく、役職や業務内容に応じて最適化することが成功の鍵です。
● 新入社員向け(導入研修)
- 情報セキュリティ・SNSの注意点
- 社内ルールやコンプライアンスの基本
- 相談・報告の重要性
▶ ポイント:まずは「リスクの存在を認識し、正しい行動を学ぶ」ことから始めましょう。
● 中堅社員向け(OJT・実務者研修)
- ヒューマンエラー防止策
- メンタルヘルスへの対応知識
- チーム内のハラスメント予防
▶ ポイント:自分だけでなく「他者への影響」にも目を向ける視点を育てます。
● 管理職・経営層向け
- 危機対応時の判断と責任の取り方
- 部下の行動管理と職場環境づくり
- BCP(事業継続計画)への理解
▶ ポイント:組織全体を守る視点から、リーダーシップと法的責任を再確認する内容が求められます。
4-3: eラーニングやマイクロラーニングの活用方法
リスクマネジメントの教育を継続的・効果的に行うには、デジタルツールの活用が非常に有効です。
特に多忙な社員にも対応できる「eラーニング」や「マイクロラーニング」は、現代的な研修手法として注目されています。
● eラーニングのメリット
- 時間や場所を問わず受講できる
- 進捗管理や理解度チェックが可能
- 全社的に統一された内容を届けられる
▶ ハラスメント対策や情報セキュリティ研修など、全社員が対象となるテーマに最適です。
● マイクロラーニングの活用例
1日5分のミニテストや短編動画などを日々の業務に組み込むことで、知識の定着率を高め、リスク感度を継続的に維持できます。
繰り返し学習によって、社員の「やってはいけない行動」が自然と減っていきます。
● ハイブリッド型の研修設計もおすすめ
対面研修でのグループワーク+eラーニングによる事前・事後学習を組み合わせることで、知識・理解・実践の3ステップが自然に身につきます。
社員教育は、リスクマネジメントを“組織文化”として根付かせるための最重要施策です。
次章では、このような教育を支える社内体制や、リスクに強い企業文化をどのようにつくるかについて、さらに深く掘り下げていきます。
5: リスクマネジメント成功のための社内体制と文化づくり

リスクマネジメントを企業内で定着させ、実効性のある仕組みにするためには、社内体制の整備と、組織全体に根付く“文化”の醸成が不可欠です。
教育や制度の導入だけで終わらせず、社員が自然とリスクに配慮した行動を取れる環境を整えることが、持続可能なリスク対策の鍵となります。
この章では、人事・教育担当者が中心となって取り組むべき「社内体制の構築」「経営層・管理職との連携」「組織文化の醸成」について解説します。
5-1: 社内におけるリスクマネジメント体制の整備方法
リスクマネジメントを機能させるには、明確な組織体制が必要です。
担当部門や責任者が曖昧なままでは、いざというときに迅速な対応ができず、被害が拡大する恐れがあります。
● 基本体制の構築ステップ
- リスクマネジメント委員会や専任チームの設置
→ 複数部門横断型で構成されるのが望ましい。人事部門も積極的に関与を。 - リスク管理ポリシー・ガイドラインの整備
→ 全社員に共通の行動指針やルールを明文化。アクセスしやすい場所に掲示。 - 内部通報制度や相談窓口の設置
→ 不正・ハラスメントなどの早期発見と対処を促進。匿名性を確保し、安心して活用できる体制を構築。 - 定期的なリスクレビュー・モニタリングの仕組み化
→ 発見・対応・再発防止のプロセスを定着させることで、リスク感度が組織全体に広がる。
社内体制が整っていない状態でいくら教育を行っても、社員は「結局どうすればいいのか分からない」となってしまいます。制度と運用の両輪を意識しましょう。
5-2: 経営層・管理職との連携と情報共有の重要性
リスクマネジメントは、現場だけで完結するものではありません。
経営層や管理職の理解と協力がなければ、社内に浸透させることは難しいのが実情です。
● 経営層の関与が持つ“重み”
経営トップが自らリスクマネジメントの重要性を発信し、具体的な行動で示すことで、組織全体に本気度が伝わります。
「形式的な取組では終わらせない」というメッセージを明確にすることが、全社的なリスク意識の醸成につながります。
● 管理職との連携による現場力の強化
現場で社員と日々接するのは、管理職です。
以下のような役割を担ってもらうことで、リスクマネジメントは現場レベルで機能しやすくなります:
- 社員からのヒヤリ・ハットの収集
- リスクを察知した際の一次対応
- チーム内での教育・注意喚起
人事部門は、管理職向けのリスクマネジメント研修や情報提供を通じて、彼らの意識とスキル向上を支援しましょう。
● 情報共有の仕組みが組織全体を守る
リスクに関する情報は「早く・正確に・全体へ」共有されることが重要です。
そのために、以下のようなツールや仕組みの導入が効果的です:
- 社内ポータルでの注意喚起やガイドライン配信
- 定例会議でのインシデント報告共有
- 共有チャネルやSlack等での速報連絡
5-3: リスクに強い組織文化を育てるためにできること
制度や教育に加えて、日々の行動や意思決定に自然とリスク意識が組み込まれている「文化」こそが、最も強力なリスクマネジメントの基盤です。
● 「言いやすい」「相談しやすい」環境づくり
心理的安全性のある職場は、リスクを隠すことなく早期に共有できる土壌を持っています。
部下の意見に耳を傾け、叱責よりも「気づき」や「学び」に変える文化を育てましょう。
● ポジティブな失敗体験の共有
リスクが顕在化したケースも、適切に振り返れば貴重な学びになります。
「あのときの失敗があったから今がある」といえるような社内風土をつくることで、社員の挑戦と改善意欲を両立できます。
● 定期的な価値観のリマインド
企業理念やミッション・ビジョンとともに、「私たちはなぜリスクに向き合うのか」を継続的に伝えることが重要です。
朝礼や全社イベント、イントラネット等を活用して、価値観を“記憶”から“習慣”へと進化させていきましょう。
リスクマネジメントは、一過性の施策ではなく、日常に根づいた「考え方」と「行動」の積み重ねによって組織力として強化されていきます。
次章では、これまでの内容を振り返りながら、人事部門として今すぐ取り組むべきアクションをまとめていきます。
6: まとめ|人事が担うリスクマネジメントで企業を守ろう

リスクマネジメントはもはや、経営陣や危機管理専門部署だけが行うものではありません。
**人事・教育部門が担う役割も年々重要性を増しており、組織全体の安全と信頼を支える“守りの要”**として、企業の成長や存続に大きく貢献しています。
本記事では、リスクマネジメントの基本から具体的な実践方法、そして社内定着のための仕組みづくりまでを総合的に解説しました。ここであらためて、ポイントを整理し、明日から実践できるアクションを明確にしていきましょう。
6-1: 本記事のポイント総まとめ
これまで解説してきた内容の中で、特に重要なポイントは以下の通りです。
- リスクマネジメントとは、企業活動におけるリスクを予測・回避・最小化する一連のプロセスであり、人事部門にも深く関わるべき領域。
- 人的リスク・ITリスク・外的リスクなど、企業内にはさまざまなリスクが存在し、それぞれに対する認識と備えが不可欠。
- 人事・教育担当者が行うリスクマネジメントの基本ステップは、「リスクの洗い出しと評価(アセスメント)」「対策の立案と実行」「PDCAサイクルによる改善」の3段階。
- 社員教育によるリスク感度の向上は、社内全体の危機対応力を高める鍵。階層別・職種別に最適な学びを提供することが重要。
- 社内体制と組織文化の整備により、制度と行動が一致する“リスクに強い組織”を構築できる。
6-2: 今すぐ実践できるアクションリスト
最後に、人事・教育担当者が今日から実行に移せる具体的なアクションをリストアップします。小さな一歩からでも構いません。できるところから着実に取り組むことで、大きなリスクを未然に防ぐ体制が構築されていきます。
✅ 1. 現在の社内リスクを洗い出すワークショップを企画する
各部署から代表者を募り、過去の事例や業務上の不安要素を共有しましょう。
✅ 2. 社員向けリスクマネジメント研修の計画を立てる
新入社員・管理職など、階層別にカリキュラムを構成し、まずはeラーニングなどからスタートを。
✅ 3. ハラスメントや情報漏洩に関する行動ルールを再確認・再周知する
ポータルや朝礼でのリマインド、社内ポスターなどで定期的な注意喚起を。
✅ 4. 内部通報制度や相談窓口の有無・機能を見直す
匿名で相談できるチャネルが機能しているか、実際にテストしてみるのも有効です。
✅ 5. 管理職向けに“現場でできるリスクマネジメント”研修を導入する
チェックリストやロールプレイを用いて、現場対応力を養う内容が効果的です。
リスクマネジメントは、「何かあったときに動く」ものではなく、「何も起こさないように整えておく」ための継続的な取り組みです。
人事部門がその中心に立つことで、組織はより安心・安全な環境となり、従業員の定着や企業ブランドの向上にもつながります。
“企業を守る人事”として、今できる一歩から始めてみましょう。
リスクマネジメントを組織に根付かせるには、日々の教育と習慣化が欠かせません。
しかし、限られたリソースの中で「伝え続ける」ことを人手だけで行うのは大きな負担です。そこでおすすめしたいのが、**毎日5分のマイクロテストでナレッジを定着させる教育サービス「kokoroe」**です。
企業理念、社内ルール、コンプライアンスなど、企業が社員に伝えたい重要知識をkokoroeが“繰り返し伝え続ける”ことで、自然と社員の行動に結びつくリスクマネジメント体制を構築できます。
「伝えたつもり」や「知っているはず」がなくなり、共通認識の浸透や、ハラスメントリスクの軽減、行動への確実な落とし込みが可能になります。
日々のテストが社員の自信と安心につながり、組織全体の危機対応力を底上げします。
リスクに強い企業文化をつくる第一歩として、「kokoroe」をぜひご活用ください。