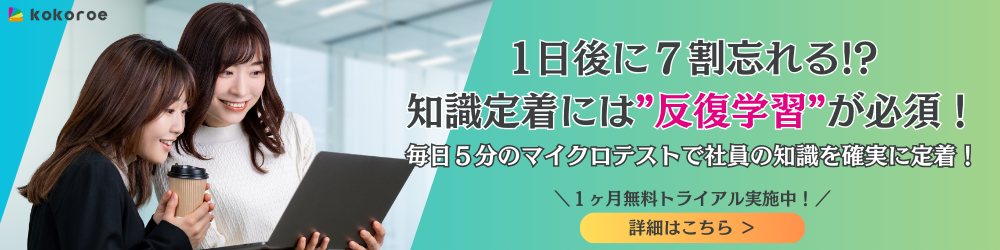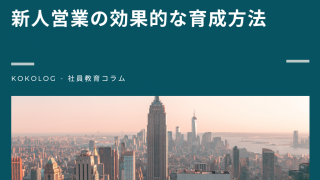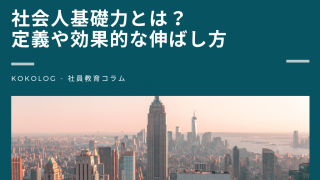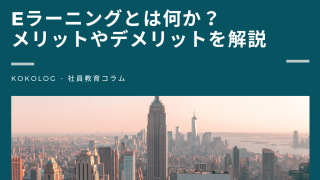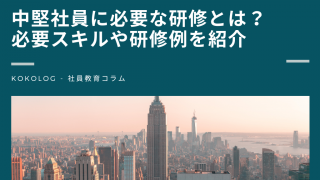「傾聴」はなぜ重要なのか?必要性や傾聴力を鍛えるコツを紹介!!
「傾聴」とは、読んで字の如く(耳を)傾けて聴くことをいいます。
耳を傾けて聴くとは、ただ話を聞くのではなく、相手の立場に立って共感し、どういった気持ち・意図で話をしているのかを理解しようと努めることです。
仕事で成果をあげるうえでは、コミュニケーションを通じてお客様やメンバー、上司などと信頼関係を築くことが重要であり、そのために「傾聴」は欠かせません。
では、傾聴力とは、どうすれば高められるものなのでしょうか。
本記事では、まず、「傾聴」とはなにか、傾聴力がビジネスで大切とされる理由を解説します。傾聴力を身につけるために実践したい5つのトレーニング方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「聞く」と「聴く」の違い

傾聴という場合、私たちが日常的によく使う「聞く」ではなく、「聴く」の漢字を用います。傾聴の具体的な特徴は、「聞く」との違いを知ることでイメージしやすくなります。
「聞く」の意味
日本国語大辞典(小学館)によると、聞くとは「音を耳で感じ取る。自然に耳に入ってくる。聞いて知る。」という意味を持ちます。
つまり、自分から行動を起こさなくても良い、受動的な状態といえます。
「聴く」の意味
一方、聴くとは「聞こうとして聞く。注意してよく聞く。」とされています。
聞くに比べると、自らの意思で行動している、つまり能動的であるといえるでしょう。
このように、「聞く」と「聴く」では意味合いが異なります。
ただ聞くだけでは、話の内容を聞き逃してしまったり、意味・意図を理解しないまま表面的に聞き流してしまうということもあるでしょう。
相手と深いコミュニケーションを取るためには、受動的に聞くのではなく、能動的に「聴く」姿勢をとることが重要です。
なぜ傾聴が大切なのか

ビジネスにおいて、傾聴力は非常に重要なスキルのひとつです。
まず傾聴の目的とは、相手が言いたいこと・伝えたいことにポイントを置いて、相手を理解することです。
傾聴では、その言葉に用いられている漢字「聴」にある通り、相手のメッセージに「耳」を傾け、声の調子や表情などに「目」で注意を払い、言葉の背後にある感情に「心」を配って話に共感します。
相手を尊重する姿勢で話を聴ける人は、自然と相手もこちらを理解してくれるようになります。深いコミュニケーションを取るためには、相手を理解し、相手も自分を理解してくれている信頼関係が必要です。傾聴はその第一歩となるのです。
傾聴力の鍛え方

では傾聴力を鍛えるためにはどうすればよいのでしょうか。
本記事では、傾聴力を鍛えるための3つの方法をご紹介します。
①会話の割合を「3:7」にする
「傾聴」と言うからには、自分が話すことよりも相手の話を聴くことの方が重要です。
よって、まず最初に意識したいのが会話の割合を「自分3:相手7」にすることです。
最初のうちは割合を意識しすぎて黙りがちになり、不自然さを感じることがあるかもしれませんが、大切なのは相手の話を理解しようとする姿勢です。
相手の話に耳を傾け、どういった意図で話をしようとしているのかを考えながら、相槌やより理解を深めるための質問を投げかけたりしてみましょう。
②相手の話に理解や共感を示す
相手の話を聴くときに大切なのが、先入観や主観にもとづくフィルターを排除して相手の話や意見を素直に受け止めることです。
アメリカの心理学者でカウンセリングの大家であるカール・ロジャーズは、傾聴を「積極的傾聴」と呼び、自らが行ったカウンセリングの事例を分析して、話を聴く側には3つの要素が必要であると説いています。
(1)自己一致(congruence)
話を聴いて分からないことをそのままにせず聴き直す等、常に真摯な態度で真意を把握する
(2)共感的理解( empathic understanding)
相手の立場になって話を聴く
(3)無条件の肯定的配慮(unconditional positive regard)
善悪や好き嫌いといった評価をせず、肯定的な関心を持ちながら話を聴く
これらの要素を意識して会話に参加することで、自然と傾聴力は高められます。
③会話テクニックを活用する
(1)ミラーリング
ミラーリングとは、相手の身振り手振りや話す姿勢、表情などを真似することで、相手が話しやすくする手法です。
ただし、ミラーリングのやりすぎが相手に気付かれた場合、不快感・警戒感を与えることになりかねません。ミラーリングを実施するときには、やり過ぎないように注意しましょう。
(2)バックトラッキング
バックトラッキングとは、いわゆる「オウム返し」のことをいいます。
例えば、「資格試験に合格したんです!」と言われたときに「資格試験に合格したんですね!」と返すのがバックトラッキングです。
バックトラッキングすることで、相手は「自分の話が相手に届いている」と安心感を持つことができるようになります。
また、パラフレーズを活用することも有効です。パラフレーズとは、相手が話した中に出てきた出来事やフレーズ等を、別の言葉で言い換えて話の中に盛り込む技法のことで、例えば「急な話で驚きました」に対して「突然のことでびっくりしましたよね」と返すように、意味を変えずに別の表現に言い換えることです。
これらの手法を上手く取り入れることで、相手に「自分の話がきちんと理解されている」という安心感を与えたり、話の内容が誰の感情、体験なのかを明確に自覚する効果があります。
まとめ

傾聴力は、メンバーやお客様との信頼関係の構築や、チームに影響力をもたらすうえで大切なスキルです。
「聞く」と「聴く」の違いを正しく理解した上で、能動的に相手の話を聴くことを意識して、深い信頼関係を築けるようにしましょう。