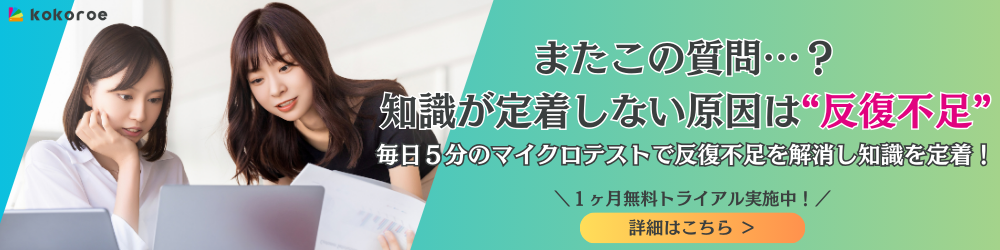当事者意識とは?職場を変える具体策10選|社員のやる気と責任感が劇的に向上!
「指示されたことしかやらない社員が多い」「もっと自分ごととして業務に取り組んでほしい」――そんな悩みを抱えていませんか?
近年、多くの企業が重視しているのが“当事者意識”です。当事者意識とは、自分の仕事に責任と覚悟を持ち、組織の一員として主体的に動く姿勢のこと。この意識が育つことで、社員のモチベーションや成長スピード、組織の成果は大きく変わります。
本記事では、「当事者意識とは何か?」という基本から、その重要性、社員の行動を変える具体策、成功事例、定着させる仕組みまでを網羅的に解説。人事・教育担当者の皆様がすぐに実践できるノウハウを厳選してお届けします。
職場を前向きに変えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1: 当事者意識とは?──意味・定義と企業が注目する理由

1-1: 当事者意識の正しい意味と「主体性」との違い
「当事者意識」とは、仕事や課題に対して“自分ごと”として捉え、責任感を持って積極的に関わる姿勢のことを指します。単に任された業務をこなすのではなく、「この仕事の成果に自分が責任を持つ」「組織の一員として貢献する」といった意識を伴う行動が、当事者意識のある状態です。
一方で混同されやすいのが「主体性」との違いです。主体性は、自ら考え行動する力を意味しますが、必ずしも“その仕事を自分の責任として引き受けている”とは限りません。
つまり、
- 主体性: 自分で考えて動く力
- 当事者意識: 自分の役割に責任と覚悟を持ち、当事者として関与する意識
と区別できます。
主体性があっても、「この仕事は自分には関係ない」と考えてしまえば当事者意識は低いままです。企業としては、この“責任感を伴う関与”が持続することを期待しており、それが当事者意識の育成につながっています。
1-2: なぜ今、当事者意識が企業で重視されているのか?
近年、当事者意識がビジネスの現場で重視される背景には、大きく3つの変化があります。
① 複雑化・変化の激しいビジネス環境
市場変化のスピードが加速し、マニュアル通りでは立ち行かない場面が増えています。上司の指示待ちではなく、社員一人ひとりが課題に気づき、自律的に動くことが求められるため、当事者意識の高さが競争力につながります。
② 組織のフラット化と権限委譲の進展
多くの企業でトップダウンからボトムアップ型の意思決定へとシフトが進んでいます。これに伴い、各社員に与えられる裁量や期待も大きくなり、「自分が組織を動かしている」という感覚がなければ成果に結びつきません。
③ 若手社員のエンゲージメント課題
Z世代をはじめとする若手社員の定着率やエンゲージメントの低さが課題となる中、「やらされている仕事」から「自分が関与する仕事」へと意識を変えるためには、当事者意識の醸成が不可欠です。
このように、当事者意識は単なる精神論ではなく、**変化の激しい現代の組織運営において必要不可欠な“基盤”**なのです。これを欠くと、社員は「他人任せ」になりやすく、責任感やモチベーションの低下、離職率の上昇にもつながってしまいます。
2: 当事者意識が低い職場に共通する3つの問題点

当事者意識が欠如している職場では、組織の生産性や社員のモチベーションに深刻な影響が及びます。ここでは、特に多くの企業で見られる代表的な3つの問題点を紹介します。
2-1: 責任の所在が曖昧で「他人ごと」になる
当事者意識が低い職場では、「自分の仕事ではない」「誰かがやるだろう」という意識が蔓延しやすくなります。これは責任の所在が明確でないことが主な原因です。
業務分担が曖昧だったり、目標や役割が共有されていないと、社員は自ら関与しようとせず、「指示がないから動かない」という状態に陥ります。結果として、仕事の質やスピードは低下し、トラブル時にも「誰の責任なのか」が曖昧になるため、組織としての信頼性が損なわれてしまいます。
責任の所在が明確であれば、社員は自然と“自分ごと”として業務に取り組むようになります。逆にそれが不明瞭な職場では、当事者意識は育ちにくく、成果も上がりません。
2-2: モチベーションが低く、行動に主体性がない
「何のためにこの仕事をやっているのかわからない」
このように感じている社員は、仕事に対するモチベーションが低くなりがちです。目的意識や意義を感じられないまま働き続けると、行動は受け身になり、指示がなければ動かない“指示待ち状態”に陥ってしまいます。
当事者意識が高い人は、自ら業務の意味や目的を見出し、前向きに動けますが、その意識がなければ、成果や課題にも関心を持てません。
これにより、「ただこなすだけの仕事」が常態化し、チーム全体の士気も下がってしまうのです。
モチベーションの低下は、一人の問題では終わりません。周囲にも消極的なムードが伝染し、職場全体の活気が失われていくのです。
2-3: 組織として成果が出にくい悪循環に陥る
当事者意識の欠如は、個人だけでなく組織全体に悪影響を及ぼします。社員一人ひとりが責任感を持たず、自発的な行動が生まれなければ、チームワークも機能せず、結果的に成果が出にくくなります。
さらに、成果が出ない→評価が下がる→モチベーションが下がる→さらに当事者意識が低下…という負のスパイラルに陥る危険もあります。
このような状態が続けば、優秀な人材の流出や離職率の上昇を招き、組織の競争力そのものが低下してしまうのです。当事者意識は、単なる“やる気”ではなく、成果を出すための土台です。この意識が職場に根付いていなければ、どんなに優れた戦略や制度があっても、実行力が伴わず、結果が出にくくなります。
3: 社員の行動を変える!当事者意識を高める具体策10選

当事者意識を育てるには、単なる「意識改革」ではなく、具体的なアクションと仕組みの導入が不可欠です。ここでは、現場ですぐに実践できる施策を10個に厳選して紹介します。
3-1: 業務の目的や意義を「言語化」する
社員が「なぜこの仕事をするのか」を理解していなければ、当事者意識は育ちません。
上司やリーダーは業務の背景・目的・社会的意義を明確に伝え、メンバーが納得感を持てる状態をつくることが重要です。
たとえば、ただ「報告書を作成する」のではなく、「この報告書が経営判断にどう役立つか」を伝えることで、社員は自らの仕事に意味を見出しやすくなります。
3-2: 成果に直結する目標設定と定期的な振り返り
当事者意識を育てるには、社員が「自分の行動が成果にどうつながるか」を理解する必要があります。
そのために有効なのが、SMARTな目標設定と定期的な振り返りの場の設置です。
「いつまでに何を達成するか」「どの指標で判断するか」を明確にし、進捗を振り返ることで、社員は自分の責任と成長を自覚しやすくなります。
3-3: 自己決定を促す裁量と任せ方
「任せる」と「丸投げ」は違います。社員に当事者意識を持たせるには、適切な裁量権を与えることが重要です。
たとえば、業務の進め方やツールの選定など、小さな範囲でも自分で決められる部分があると、社員は責任を持って取り組むようになります。「あなたに任せたい」というメッセージは、社員の自己決定感と責任感を引き出す強力なトリガーです。
3-4: フィードバックと称賛を即時に伝える
良い行動には即時のフィードバックを。タイムリーなフィードバックは、社員の行動を“自分ごと”として定着させる鍵です。
「よかった点」「改善できる点」を具体的に伝えることで、社員は自分の仕事への意識を深められます。さらに、称賛を伴うフィードバックは、自己肯定感を高め、次の行動につながる原動力にもなります。
3-5: ロールモデルの行動を見せて巻き込む
「上司がどう動いているか」を社員は見ています。口だけでなく、行動で示すロールモデルの存在は、当事者意識を育てる上で非常に効果的です。
たとえば、上司が率先して課題に取り組んだり、自らの失敗を開示することで、部下は「自分も関わるべきだ」と自然に行動しやすくなります。姿勢や姿を見せることで巻き込むことができます。
3-6: チームで失敗を許容する文化を築く
当事者意識を持った行動には、失敗のリスクがつきものです。失敗を咎める文化があると、社員は挑戦を避け、“他人任せ”に逃げがちになります。
大切なのは、失敗を成長の材料と捉える文化です。たとえば「なぜ失敗したか」「何を学んだか」をチームで共有する場を設ければ、前向きな挑戦が促され、当事者意識が根づいていきます。
3-7: 個人の成功体験を社内で共有する
「誰かの成功」は、他の社員の意識を変える力があります。社員が自分の意思で動いて成果を出したエピソードを社内で紹介することで、当事者意識の好循環を生み出せます。
特に、同じ立場の社員の事例は共感を呼びやすく、「自分にもできるかもしれない」という意識変化を促します。小さな成功でも、積極的に共有しましょう。
3-8: 上司が「見てくれている」安心感を与える
誰にも見られていないと、人は手を抜きがちです。逆に「ちゃんと見てくれている」「評価してくれている」という感覚があれば、社員は当事者としての自覚を持ちやすくなります。
定期的な1on1や声かけ、業務の進捗に対するリアクションなど、日常的なコミュニケーションを大切にしましょう。上司の「見守り」は、社員の責任感を育てる土壌になります。
3-9: 社員教育に反復と実践を取り入れる
単発の座学では、当事者意識は育ちません。重要なのは、反復学習と実践を通じた知識定着と行動変容です。
たとえば、日々のマイクロラーニングや小テスト形式の教育は、短時間で効果的に知識を習得でき、業務との結びつきも強化されます。知識が腹落ちすれば、行動に責任が伴うようになり、当事者意識が自然と育ちます。
3-10: 知識と目標を「共通言語」にする仕組みを持つ
「誰が、何を、どこまで理解しているか」がバラバラでは、組織全体に一体感は生まれません。理念や業務知識、目標を共通言語として“見える化”する仕組みが必要です。
たとえば、定期的に全社で知識を確認し合ったり、ビジョンや目標を全員で確認する場を持つことで、各自が「組織の一員」としての自覚を持ちやすくなります。
これら10の施策を地道に積み上げていくことで、社員一人ひとりが仕事を“自分ごと”として捉え、行動・成果・責任感すべてが変化していきます。
4: 成果が出る職場はここが違う!当事者意識の成功事例

当事者意識を高める施策を取り入れることで、実際に成果を上げている企業は数多く存在します。この章では、「若手の成長」と「離職率の改善」という視点から、注目すべき2つの事例を紹介します。
4-1: 若手の成長スピードが加速したIT企業の例
ある急成長中のIT企業では、若手社員の“指示待ち傾向”が組織全体の課題になっていました。特にプロジェクトの進行において「リーダー任せ」「自分の担当範囲だけやる」といった姿勢が目立ち、納期遅延やクオリティのばらつきが頻発していたのです。
そこでこの企業は、「全社員がプロジェクトの“当事者”である」という意識を醸成するために、以下のような取り組みを実施しました。
- 業務の背景や最終的な目的を毎週共有
- 自由度の高いタスク設計と裁量権の付与
- 小さな成功事例の全社共有会の定期開催
- 上司・メンターによる週次1on1と称賛フィードバック
これらの施策により、若手社員の自走力が大きく向上。実際に入社1年目でプロジェクトリーダーを担う社員が現れるなど、成長スピードの加速が明確に見られました。
社員アンケートでも「自分の仕事がプロダクトの成果に直結していると感じる」「意見を言いやすくなり、行動量が増えた」という声が多く寄せられ、当事者意識の浸透が成果と直結していることが裏付けられました。
4-2: 自分ごと化で離職率を半減させた中堅メーカー
従業員300名規模の中堅メーカーでは、数年間にわたり若手の離職率が20%以上と高止まりしており、社内では「新卒がすぐ辞める会社」との認識が広がっていました。
原因を探ったところ、「配属後の業務が受け身で面白みを感じられない」「自分の仕事が会社にどう貢献しているのかわからない」といった不満が根底にあることが判明しました。
そこでこの企業は、“自分ごと化”をキーワードに次のような取り組みをスタートさせました。
- 各部門での業務目的の可視化と言語化
- 業務改善提案制度の導入(実行されたらポイント付与)
- 週1回のリーダーとの対話機会(成果・貢献のフィードバックを中心に)
- 教育ツールを活用した日次の振り返りと気づきの共有
結果として、社員の仕事への納得感と自己決定感が高まり、翌年には離職率が9%台に半減。また、自ら改善提案を出す社員が増え、工場の生産性や安全管理面にも良い影響が出るようになりました。
この事例は、「一人ひとりが自分の業務を“会社の未来に直結するもの”と認識したとき、定着率とエンゲージメントは劇的に改善する」ことを証明しています。
このように、当事者意識を育てる取り組みは人材の成長と組織の成果の両方に好影響をもたらすことが明らかです。次の章では、こうした効果を一時的で終わらせず“定着”させるための教育施策について解説します。
5: 当事者意識を「定着」させる仕組み──教育の仕方を変える

当事者意識を高めるために施策を導入しても、それが一過性で終わってしまっては意味がありません。本当に効果を発揮するのは、「継続的な定着」によって行動が変わるときです。この章では、当事者意識を持続・習慣化させるための教育のあり方について解説します。
5-1: 一過性の研修では定着しない理由
多くの企業で行われている「1回きりの研修」や「年1回の集合型セミナー」では、学んだ内容が定着せず、行動変容にはつながりにくいのが現実です。
その理由は以下の通りです。
- 忘却曲線の存在:人は1日後には約70%の情報を忘れてしまうと言われており、復習がなければ内容は記憶に残りません。
- 実務との結びつきの弱さ:研修と日常業務が断絶していると、学びが“自分ごと”になりにくく、当事者意識を育む土壌ができません。
- 受け身の学習体験:講義形式の研修は受講者が受け身になりやすく、主体的な気づきや行動の変化が起きにくくなります。
一過性の教育では、意識の一時的な向上はあっても、組織文化や行動様式として根づくことはありません。重要なのは、日々の業務と結びついた「継続的な仕組み」を作ることです。
5-2: 毎日の学習習慣で「行動」を変える方法
当事者意識を定着させる鍵は、「毎日の少しの学習」と「反復」にあります。いわゆる**マイクロラーニング(短時間・高頻度の学習)**は、記憶定着だけでなく、社員の思考や行動にも大きな影響を与えます。
たとえば次のような仕組みが有効です。
- 1日5分のマイクロテスト:理念や業務知識に関する小テストを毎日出題することで、知識が自然と定着し、意識が継続的に刺激される。
- 業務前の“思考スイッチ”として活用:学習の内容がその日の業務とリンクしていれば、仕事への関与度が高まる。
- 反復で「気づき」を強化:繰り返し同じテーマに触れることで、「この考え方を自分のものにしよう」という意識が育つ。
継続的な学習があることで、社員は会社のビジョンや業務知識を“自分の言葉”で語れるようになり、それが当事者としての行動に直結します。
5-3: 知識・理念・目標の“共有”と“理解”を深める
当事者意識を根づかせるには、知識の一方通行な伝達ではなく、「共有」と「理解」の仕組みが不可欠です。これは、単なる情報提供ではなく、社員一人ひとりが「自分はどう捉えたか」「どのように活かすか」を考えるプロセスです。
以下のようなアプローチが効果的です。
- 共通言語としての理念浸透:企業理念や行動指針を具体的なエピソードとセットで伝え、全社員が同じ認識を持てるようにする。
- ナレッジの可視化と対話:FAQや業務ルールを共有するだけでなく、それについてディスカッションする機会を設ける。
- 目標のリンク:組織全体の目標と個人の業務目標がどうつながっているかを明示し、「自分の役割」を明確化する。
理解と共有が深まることで、社員は「言われたからやる」のではなく、「自分の役割として取り組む」状態になります。これこそが、当事者意識の定着につながる最も本質的な変化です。
このように、当事者意識を“育てる”だけでなく“定着させる”には、教育の方法自体を見直す必要があります。次の章では、こうした学びを仕組み化し、日常業務に取り込む最適な方法として、自社で導入できるツールやサービスについて解説します。
6: 当事者意識を高めるなら「kokoroe」──反復学習で変わる組織

当事者意識を高めるには、単発の研修や啓発ではなく、日常的に学び・考える“習慣”の形成が不可欠です。そこで注目されているのが、反復学習を通じて行動変容を促す教育ツール「kokoroe」です。
kokoroeは、社員一人ひとりに必要な知識を毎日5分のマイクロテストで届けることで、記憶定着と意識づけを同時に実現。理念浸透・ナレッジ共有・自律的な行動の促進までをサポートします。
6-1: 毎日5分のマイクロテストで記憶を定着
kokoroe最大の特長は、“毎日5問・5分”で完結するマイクロテスト形式の学習です。これにより、業務の合間でも無理なく学び続けることができ、知識の忘却を防ぎます。
- 忙しい社員でも継続できる“習慣設計”
- AIによる自動出題で、記憶に残りやすい反復パターンを最適化
- 復習機能で「学びっぱなし」にならない仕組み
こうした仕組みにより、社員は「知っているつもり」ではなく、「使える知識」としてナレッジを体得。日々の学習を通して、自然と当事者意識が育ちます。
6-2: 自社のナレッジや理念を“自分ごと”化できる
kokoroeでは、業務知識・商品理解・社内ルール・コンプライアンスなど、自社独自のナレッジを反映したテストを柔軟に設計できます。さらに、理念やビジョンの浸透も、マイクロテストを通して“反復”されることで、単なる暗記ではなく、“自分ごと”として理解されるレベルにまで深まります。
- 自社の資料やマニュアルからAIが自動で問題を生成
- 問題文や選択肢も簡単にカスタマイズ可能
- 理念や方針を日常的に問い直す設計で「腑に落ちる」
これにより、「会社が大切にしていること」を全社員が同じ言葉で理解し、それを日常行動に落とし込めるようになります。
6-3: 行動のズレをなくす共通認識づくりに最適
当事者意識が組織に根づくには、全員が“同じ地図”を持って動ける状態=共通認識の形成が不可欠です。kokoroeでは、社員の理解度や学習履歴を可視化できるため、「誰が何を理解しているか」「どこで差が出ているか」が一目で把握できます。
- 個人・チーム単位での定着度の見える化
- 認識のズレを“気づける”から修正できる
- 成果や傾向に応じた追加学習の設計も簡単
このように、kokoroeは知識の伝達手段であるだけでなく、「行動のズレを未然に防ぐナレッジマネジメントツール」として、組織の一体感を生む基盤となります。
当事者意識を高め、組織のパフォーマンスを底上げしたいとお考えなら、まずは「学びの仕組み」から変えてみませんか?
kokoroeなら、継続的な学習×自分ごと化×成果の見える化で、社員の意識と行動を確実に変えていくことができます。
資料請求や無料トライアルも可能ですので、ぜひ一度ご検討ください。成、全体像の把握を通じて、当事者意識を自然と高める環境を作りましょう。