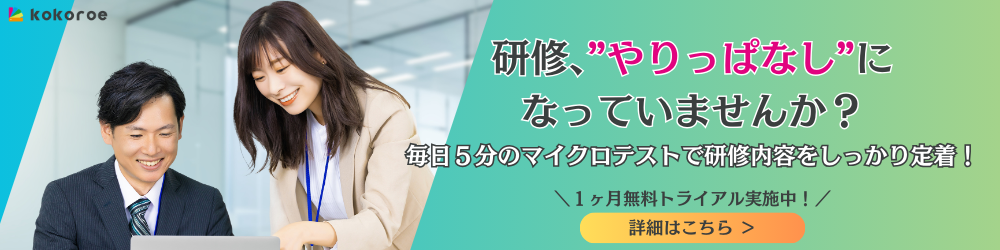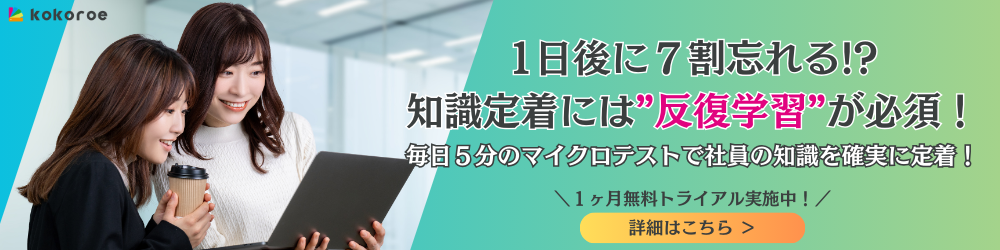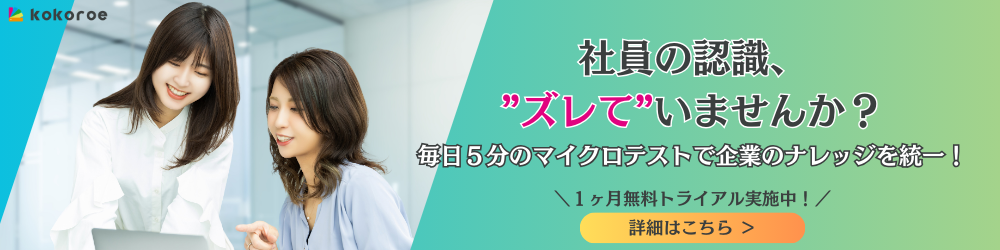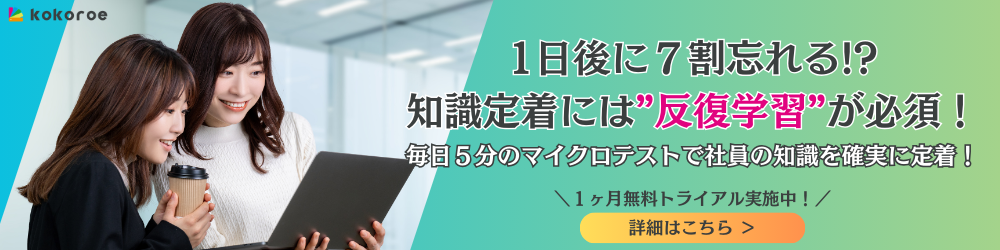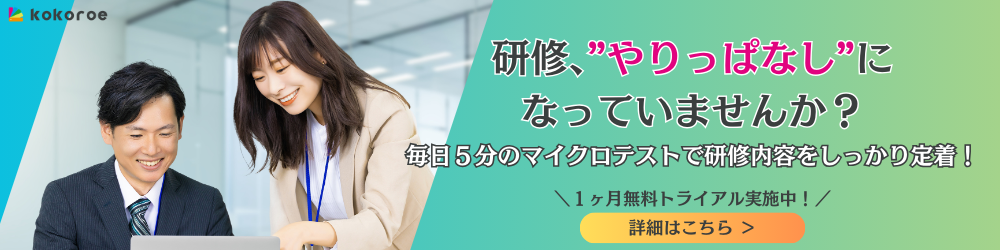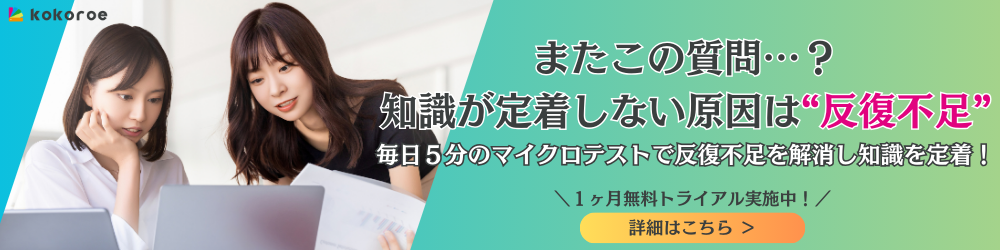なぜ「パーパス経営」が注目されるのか?その背景とメリットを解説
「パーパス経営」とは、企業が単なる利益追求を超えて、自らの存在意義や社会的価値を経営の軸に据えるスタイルです。
近年、消費者や投資家が企業の社会貢献や持続可能性に注目する中、パーパス経営は企業の競争力や信頼性を高める重要な要素として注目されています。
本記事では、パーパス経営の基本から、そのメリットや導入方法、業界ごとの成功事例までを初心者にもわかりやすく解説します。企業が社会にポジティブな影響を与えながら成長を目指すための実践的なガイドとして、ぜひご覧ください。
1: パーパス経営とは?その基本と意味

パーパス経営とは、企業の「存在意義」や「目的(パーパス)」を基盤にした経営スタイルのことです。
従来の経営は、利益を上げることを目的としていましたが、パーパス経営では、企業が社会や顧客にとってどのような価値を提供するのか、またどのように社会貢献をするかに焦点を当てています。
利益追求だけでなく、企業としての使命を果たすことで、顧客や従業員、さらには社会全体からの信頼を得ることができるのがパーパス経営の特徴です。
1-1: パーパス経営の定義と背景
パーパス経営の定義は「企業が持つ社会的な使命や価値観を経営の中心に据え、事業活動に反映させること」です。
パーパス経営は、社会の期待や持続可能な発展への関心が高まる中で注目され始めました。企業が果たす役割が多様化し、単に利益を追求するだけでなく、社会や環境問題への貢献が求められています。
特に近年では、持続可能な開発目標(SDGs)や企業の社会的責任(CSR)が重視される中で、企業も「社会にとっての存在意義」を再定義し、それに基づいた経営を行うことが重要視されています。
1-2: パーパスとは何か?
「パーパス」とは、企業が存在する目的や意義を意味します。
単に売上や利益を上げるために存在するのではなく、社会にどのような良い影響をもたらすか、何を実現したいのかという「目的意識」が含まれます。
例えば、ある食品メーカーが「人々の健康を支える食品を提供する」というパーパスを掲げている場合、それがその企業のすべての活動に影響を与え、製品開発やマーケティング戦略、企業の文化にまで反映されることになります。
1-3: パーパス経営の重要性
パーパス経営が重要視される理由には、いくつかの要素があります。
- 顧客との信頼関係の構築
パーパスを明確にすることで、企業の価値観に共感する顧客が増え、ブランドの支持が高まります。単なる製品やサービスの提供ではなく、顧客と企業が価値観を共有することが可能となり、長期的な信頼関係が築けます。 - 従業員のエンゲージメント向上
企業のパーパスが明確だと、従業員もその目的に共感し、日々の仕事にやりがいを感じやすくなります。自分が働く会社が社会貢献や価値ある目標を持っていると感じることで、社員のモチベーションが高まり、エンゲージメントが向上します。 - 社会からの評価
企業が持つパーパスが明確であると、社会からの支持や信頼を得やすくなります。特に、環境や人権に配慮した活動を行う企業は、ステークホルダーや投資家からも注目されやすく、持続的な成長が見込まれます。
パーパス経営を取り入れることにより、企業は利益だけでなく、社会にとっても重要な存在となり、結果として長期的な成長と安定を実現しやすくなります。
2: パーパス経営が注目される理由

ここ数年、企業が単に利益を追求するだけでなく、社会や環境に貢献する「パーパス経営」が注目されています。
では、なぜパーパス経営がこれほど重要視されるようになったのでしょうか?背景には社会の変化や新しい世代の価値観、持続可能な成長の必要性があります。
2-1: 社会的な背景とニーズ
「パーパス経営とは、企業の存在意義を追求し、社会貢献を目指す経営スタイル」といえます。このような経営が求められる背景には、消費者や社会全体の意識の変化があります。
従来は、企業は利益を上げることが最も重要な役割と考えられてきましたが、近年では環境問題や人権問題などへの配慮が重視されるようになりました。特に地球温暖化や資源の枯渇といった環境問題が深刻化する中で、企業も社会に対する責任を果たすことが求められています。
現代の消費者は、企業が社会にどのような価値をもたらしているかを見ており、その価値に共感した企業の製品やサービスを選ぶ傾向が強まっています。
このため、企業は単なる商品やサービスの提供だけでなく、自社のパーパスを通して社会にどのように貢献しているかを示す必要があるのです。
2-2: ミレニアル世代とZ世代の影響
パーパス経営と聞くと難しそうに思えるかもしれませんが、特にミレニアル世代やZ世代にとっては非常に重要な概念です。これらの世代は、環境保護や社会的な公正に対する関心が高く、自分が働く企業や消費する企業にもその価値観を求める傾向があります。
つまり、企業が「何のために存在するのか」「社会にどのように貢献しているのか」が、彼らの選択に大きな影響を与えるのです。
この新しい世代は、企業の透明性や社会貢献を重視し、パーパス経営を行う企業を支持する傾向があります。
たとえば、ある企業が環境保護に取り組んでいることを知れば、その企業の商品を購入したり、働きたいと考えるようになります。企業にとっても、この世代からの支持を得ることは将来の成長につながるため、パーパス経営の導入が重要になっているのです。
2-3: 持続可能性とSDGsの視点
パーパス経営とは、持続可能な未来を目指す経営スタイルでもあります。
持続可能な開発目標(SDGs)は、2030年までに達成すべき17のグローバルゴールとして国連が掲げたもので、貧困や環境問題、平等な教育など、社会が解決すべき課題が含まれています。多くの企業がこのSDGsに共感し、自社の経営方針に反映させる動きが進んでいます。
パーパス経営を取り入れることで、企業はSDGsの目標に貢献しながら、社会的に意義のある活動を行うことができます。
たとえば、ある企業が再生可能エネルギーの活用を推進することでSDGsの「エネルギーの持続可能性」への貢献を果たしているといったように、パーパス経営を通じて持続可能な成長が可能になります。こうした取り組みは、社会や投資家からの評価を高め、長期的に見ても企業価値を向上させるメリットがあります。
3: パーパス経営のメリットとは

パーパス経営を導入することで、企業はただ利益を追求するだけでなく、社会的な価値を提供し、長期的に成長できる体制を築くことができます。
では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、パーパス経営がもたらす3つの重要なメリットについて解説します。
3-1: 企業の競争力向上
「パーパス経営とは、企業の存在意義を明確にし、それを経営の中心に据えること」と説明されます。このアプローチにより、企業は他社との差別化を図ることができます。
たとえば、社会貢献を掲げている企業は、消費者や取引先から特別な評価を受けやすくなり、同業他社との差別化が可能になります。また、パーパス経営を通じて築いたブランド価値は、企業の競争力を向上させ、価格競争に陥らずとも支持を得られるようになるのです。
さらに、企業のビジョンやパーパスに共感する顧客や投資家が増えることで、ブランドの認知度が高まり、安定したビジネス基盤を構築できるようになります。このように、パーパス経営を取り入れることで、他社にはない独自の強みを持つことができ、結果として競争力が向上するのです。
3-2: 従業員のエンゲージメント向上
パーパス経営とは、従業員にとっても非常に魅力的な経営スタイルです。企業が社会的意義を持つパーパスを掲げることで、従業員は自分の仕事に誇りを持ち、やりがいを感じるようになります。
自分が所属する企業が単に利益追求だけでなく、社会や顧客のために貢献していることを知ると、従業員のモチベーションが上がり、エンゲージメント(仕事への関与度)も向上するのです。
また、パーパス経営を導入している企業は、従業員の成長を支援するための研修や教育にも力を入れることが多く、自己成長を求める従業員が集まりやすいという特徴もあります。従業員が自分の仕事を通じて企業のパーパスに貢献できると感じることで、企業全体の士気が高まり、生産性の向上にもつながります。
3-3: 顧客との信頼関係の強化
「パーパス経営とは、企業が社会にどのような価値をもたらすかを重視する経営スタイル」です。こうした企業は、顧客にとっても魅力的な存在です。
企業の理念やパーパスに共感する顧客が増えることで、企業と顧客との間に強い信頼関係が生まれます。特に、企業が透明性を保ち、社会や環境に貢献する姿勢を示すことで、顧客からの支持が厚くなるのです。
顧客が商品やサービスを購入する際に、その企業のパーパスに共感できると、価格や品質だけでなく、企業の姿勢や価値観にも注目するようになります。これにより、顧客はその企業のファンになり、リピート購入や口コミによる新規顧客の増加にもつながります。信頼関係が強化されることで、企業は安定した売上基盤を確保できるようになるため、長期的な成長が可能となります。
4: パーパス経営の失敗事例

パーパス経営が企業に多くのメリットをもたらす一方で、取り入れ方によっては失敗するリスクも存在します。実際に、パーパス経営を掲げているにもかかわらず、失敗してしまう企業も少なくありません。
ここでは、パーパス経営における失敗事例として、よくあるリスクやそこから得られる教訓、注意すべき点と対策について解説します。
4-1: パーパスウォッシュのリスク
「パーパス経営とは、企業の存在意義を明確にし、それを軸に経営を行うスタイル」とされていますが、この考え方を単なるマーケティング手法と見なすと、「パーパスウォッシュ」のリスクが高まります。
パーパスウォッシュとは、企業が表面的にパーパス(存在意義)を掲げているだけで、実際にはその理念に沿った行動をしていない状況を指します。
たとえば、環境保護を謳っている企業が実際には環境への配慮が乏しい活動をしている場合や、社会貢献をアピールしながらも従業員の労働環境が悪い場合などがパーパスウォッシュの典型例です。こうした矛盾が顧客や社会に明らかになると、企業の信頼が損なわれ、逆効果になるリスクがあります。
4-2: 失敗から学ぶ教訓
パーパス経営が失敗するケースから学べる教訓として重要なのは、「企業のパーパスを実際の行動に落とし込むこと」です。
単にスローガンやキャッチコピーとしてパーパスを掲げるだけではなく、実際にその理念に基づいた活動をしなければ、顧客や従業員からの信頼を得ることはできません。
たとえば、ある企業が「従業員の幸福を大切にする」と掲げながらも、実際には長時間労働や低賃金が続いている場合、従業員はそのパーパスに共感できず、モチベーションが低下します。その結果、離職率が上がり、企業としての競争力が低下する可能性が高まります。
パーパス経営の成功には、経営陣が率先してパーパスを行動に反映させる姿勢が求められます。
4-3: 注意すべき点と対策
「パーパス経営とは、企業の活動全体に存在意義を反映させること」が基本です。そのため、失敗を避けるためには以下の点に注意する必要があります。
- 表面的なアピールにとどめない
パーパスを表面的に掲げるだけでは、顧客や従業員の共感を得ることはできません。実際にパーパスに基づいた行動が伴っているか、内部でのチェックが重要です。たとえば、環境への配慮を掲げるなら、再生可能エネルギーの使用や資源のリサイクルなど、具体的な取り組みが求められます。 - 従業員の理解と共感を得る
パーパス経営が成功するためには、従業員がそのパーパスに共感し、自らの仕事に活かすことが大切です。そのために、パーパスを策定する際には従業員の意見を取り入れたり、定期的にパーパスについて共有し、浸透させる活動を行うことが推奨されます。 - 定期的な評価と改善
パーパス経営を続けるためには、定期的に活動を振り返り、改善点を見つけることが大切です。実際の行動がパーパスに沿っているか、効果的に顧客や従業員に価値を提供できているかを評価し、改善を図ることで、企業の成長が持続可能になります。
これらの点を意識しながらパーパス経営を進めることで、パーパスウォッシュのリスクを避け、信頼される企業としての地位を確立することが可能になります。
5: パーパス経営の具体的な策定方法
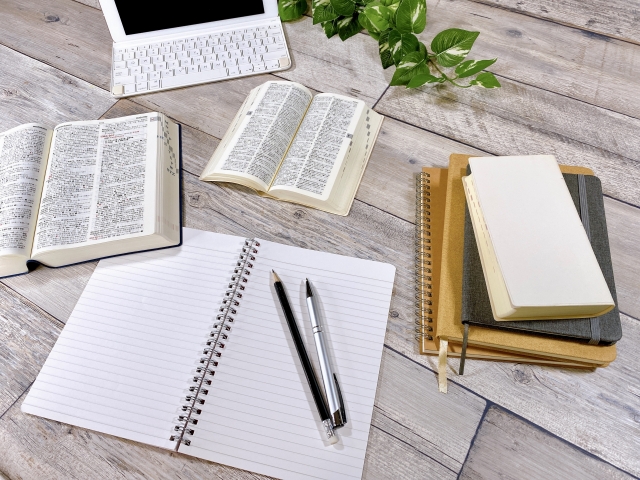
パーパス経営を成功させるには、企業の存在意義を明確にし、ビジョンを策定して浸透させることが重要です。また、パーパスを具体的な業務に反映させることで、企業全体が一貫した方向に進むことができます。
ここでは、パーパス経営の具体的な策定方法を3つのステップに分けて解説します。
5-1: 自社の存在意義の明確化
「パーパス経営とは、企業が存在する目的や社会的意義を軸に経営を行うこと」と言えます。そのため、まずは自社が「なぜ存在するのか」「何を目指すのか」を明確にする必要があります。このプロセスでは、企業の創業当初の理念や、現在の社会や顧客に対する価値提供について振り返り、再確認することが重要です。
存在意義を明確にするためには、次の質問を自社に問いかけてみましょう。
- 当社は何を大切にしているのか?
- 社会や顧客にどのような価値を提供しているか?
- 他社とは何が異なり、なぜ自社が必要とされているのか?
このようにして明らかになった存在意義は、企業全体の指針として、従業員や顧客に伝えるべき核となります。
5-2: ビジョンの策定と浸透
「パーパス経営とは、企業が目指す方向性を示し、全従業員が共感しやすいビジョンを策定すること」でもあります。存在意義を明確にしたら、その意義に基づいて企業のビジョンを設定します。ビジョンは、企業がどのような未来を目指しているかを表し、従業員がその目標に向かって行動するための指針となります。
ビジョンを策定する際には、具体的でわかりやすく、従業員全員が理解しやすい内容にすることが大切です。そして、策定したビジョンを社内で共有し、浸透させるための活動を行います。
たとえば、定期的にビジョンに関するワークショップや研修を開催したり、企業の活動の場面でビジョンに基づいた取り組みを紹介したりすることで、ビジョンが従業員の日常業務に根付いていきます。
5-3: 具体的な業務への反映
パーパス経営とは、企業のビジョンやパーパスが経営理念だけでなく、実際の業務や行動にも反映されることが理想です。ビジョンを策定し浸透させた後は、それを具体的な業務にどのように反映させるかが重要なポイントです。
具体的な業務への反映方法としては、たとえば次のような方法が考えられます。
- 製品やサービスの開発:パーパスに沿った価値提供を目指し、顧客や社会に貢献する製品やサービスを開発します。
- 従業員の評価基準の見直し:パーパスやビジョンに基づいた行動を評価基準に取り入れ、従業員がその理念を実践する意識を高めます。
- 日々の業務改善:パーパスに照らして改善できる点を常に見つけ出し、業務の効率化や社会貢献に繋がるプロセスを取り入れます。
これらの具体的な反映により、パーパスが単なる理念に留まらず、企業のすべての行動に活かされるようになります。これが実現できれば、従業員も企業が目指すパーパスを実感し、仕事に誇りとやりがいを感じるようになります。
6: パーパス経営の評価と効果測定

パーパス経営を効果的に行うためには、実行状況を評価し、成果を測定するプロセスが欠かせません。パーパス経営がどのように企業の成長や社会への貢献に結びついているのかを明確にすることで、継続的な改善が可能になります。
ここでは、パーパス経営の評価と効果測定の方法を3つのステップで解説します。
6-1: 評価指標の設定方法
「パーパス経営とは、企業の存在意義を基にした経営」であり、その効果を測るためには、評価指標を明確に設定することが重要です。パーパス経営の評価指標は、単なる売上や利益だけでなく、パーパスに基づいた活動がどのような影響をもたらしているかを測るものにします。
評価指標の設定には、以下の要素が参考になります。
- 従業員のエンゲージメント:従業員が企業のパーパスに共感し、自分の仕事に誇りを持っているかを測定するために、従業員満足度調査やエンゲージメントスコアを活用します。
- 顧客からのフィードバック:顧客がパーパスに共感しているか、パーパスが製品やサービスに反映されているかを顧客満足度調査やレビューなどで確認します。
- 社会や環境への影響:環境保護活動の成果や、地域社会への貢献度など、企業のパーパスが社会的にどれほどの影響を与えているかを数値化できる指標を設定します。
これらの指標を設定することで、パーパス経営が企業にもたらす具体的な効果を可視化できるようになります。
6-2: 実行と結果のフィードバック
「パーパス経営とは、目指す方向性に基づいて日々の業務を改善し続けること」でもあります。設定した評価指標に基づいて実行した活動の結果を定期的にフィードバックすることで、企業はパーパス経営の効果を確認し、必要な改善策を講じることができます。
フィードバックのプロセスでは、経営陣だけでなく従業員全体で結果を共有することが重要です。たとえば、パーパス経営が顧客満足度の向上に繋がっているか、環境への貢献がどのように実現できているかなどを定期的に報告し、従業員のモチベーションを高めるきっかけとします。
また、従業員からも直接意見を集め、現場での課題や改善点を反映させることで、全員が一丸となってパーパスに沿った活動に取り組める環境が整います。
6-3: 長期的な成長の追求
パーパス経営とは、企業の短期的な利益を追求するのではなく、社会と共に長期的に成長することを目指す経営スタイルです。そのため、短期的な成果だけでなく、長期的な成長を見据えた評価が必要です。パーパスに基づいた取り組みが企業のブランド価値や顧客からの信頼を高め、企業としての持続可能性を強化するため、長期的な視点での効果測定が求められます。
長期的な成長を追求するには、次のようなポイントを意識しましょう。
- 定期的な見直し:パーパス経営の活動が企業の成長にどう影響しているかを定期的に見直し、戦略の方向性を調整します。
- 柔軟な対応:社会や顧客のニーズが変化する中で、パーパスの達成方法や活動の優先順位を見直し、企業としての成長を支える体制を整えます。
- 長期的なパートナーシップの構築:顧客や地域社会、投資家といったステークホルダーと信頼関係を築き、長期にわたってパーパスを実現できる関係を育てます。
パーパス経営が企業に根付き、長期的な成長を実現するためには、こうした長期視点での評価と改善が欠かせません。
7: パーパス経営とDXの関係

「パーパス経営とは、企業の存在意義や社会的価値を経営の中心に据えること」とされていますが、近年、この考え方とデジタルトランスフォーメーション(DX)が密接に結びついています。DXは企業がデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや業務を変革することで、パーパス経営を実現するための重要な要素となっています。
ここでは、パーパス経営とDXの関係について、DXの基本的な意味から具体的な技術、企業文化との調和までを解説します。
7-1: デジタルトランスフォーメーションの意味
デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、デジタル技術を活用して企業のビジネスモデルや業務プロセスを変革することです。従来の業務を効率化するだけでなく、新しい価値を創出し、顧客や社会に貢献することが目的です。
たとえば、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティングなどの技術を活用することで、データに基づいた迅速な意思決定が可能になり、企業が持つパーパスをより効果的に実現できるようになります。
DXを通じて業務を変革することで、パーパス経営において重要な「社会的価値の提供」や「顧客のニーズへの対応」が一層スムーズに進むようになり、企業の成長にとっても大きなメリットとなるのです。
7-2: パーパス経営を推進する技術
「パーパス経営とは、企業が掲げる存在意義を社会に対して実現すること」を目指すものであり、DXの技術はその実現を強力にサポートします。ここでは、パーパス経営を支える具体的な技術について解説します。
- データ分析とAI:データ分析やAI(人工知能)は、顧客のニーズや社会のトレンドを把握し、迅速な対応を可能にします。たとえば、顧客のフィードバックをAIで分析し、企業のパーパスに沿った製品やサービスを改善するなど、顧客や社会に価値を提供する方法が強化されます。
- クラウド技術:クラウド技術を活用することで、情報の共有が迅速化し、リモートワークでもチーム全体がパーパスに基づいた意思決定を行いやすくなります。特に企業が分散している場合でも、クラウド上でパーパスに関わるデータを一元管理することで、全社員が一貫した方針で行動することができます。
- IoT(モノのインターネット):IoT技術を活用することで、実際の業務や製品に関するリアルタイムのデータを取得できるため、企業の活動が社会や環境に与える影響を適切に管理し、パーパスに沿った改善を行うことが可能です。
これらの技術を活用することで、企業のパーパスが単なる理念にとどまらず、具体的な活動として推進できるようになります。
7-3: DXと企業文化の調和
「パーパス経営とは、単なる業績向上だけでなく、企業が社会的責任を果たすための経営スタイル」です。一方で、DXを導入する際には、企業文化との調和が重要です。
デジタル技術を活用することで業務効率が上がる一方、従業員がその変化についていけない場合や、組織内でパーパスが十分に共有されていない場合、DXによって新たな課題が生じる可能性もあります。
DXとパーパス経営を調和させるためには、以下のポイントが重要です。
- 従業員への教育とサポート:新しいデジタル技術が導入される際、従業員がそれを理解し、パーパスに基づいた業務ができるよう研修を行うことが必要です。従業員がDXの重要性とパーパスの結びつきを理解することで、全員が一体となって企業の目標に向かうことが可能になります。
- 企業全体での価値観の共有:DXが進む中でも、企業のパーパスや価値観を明確にし、それを共有することが大切です。全社員がパーパスに共感し、それに基づいた行動を取るようにすることで、技術と企業文化が調和し、企業の一貫性が保たれます。
- フィードバックの重視:DXの導入によりデータが活用されやすくなるため、定期的に社員からのフィードバックを収集し、パーパスに沿った改善を進めることが重要です。特に現場で働く従業員が感じる問題点や改善案を反映させることで、DXによってパーパス経営がより強固なものになります。
このように、DXと企業文化を調和させながらパーパス経営を進めることで、企業は社会的意義のある活動を持続的に行うことができるようになり、従業員の満足度や企業の信頼性向上にもつながります。
8: 業界ごとのパーパス経営の事例

パーパス経営は多くの業界で取り入れられ、企業ごとに様々なアプローチが行われています。それぞれの業界の特徴に合わせて、独自のパーパスを掲げ、社会に貢献しながら成長を目指しています。
ここでは、成功した企業の事例、業界ごとのアプローチの違い、そして学ぶべきトレンドと手法について解説します。
8-1: 成功した企業の事例分析
「パーパス経営とは、企業が存在意義を追求し、社会に対してどのような価値を提供するかを基盤にした経営スタイル」です。ここでは、いくつかの業界でパーパス経営を成功させた企業の事例を見てみましょう。
- 食品業界:ある大手食品メーカーは「人々の健康と幸福を支える」をパーパスに掲げ、低カロリーや有機食品の開発に力を入れています。この企業は、製品の栄養価に関する透明性を高め、健康志向の消費者から支持を集めています。
- テクノロジー業界:あるテック企業は「世界をつなげることで可能性を広げる」というパーパスを掲げ、インターネットアクセスが難しい地域へのインフラ提供に取り組んでいます。このパーパスに基づく活動が企業の評判を向上させ、グローバルな市場での影響力を強化しています。
- 自動車業界:ある自動車メーカーは「環境に優しい移動手段を提供する」をパーパスに掲げ、電気自動車やハイブリッド車の開発を進めています。この取り組みによって、環境への配慮を重視する顧客から支持を得ており、業界全体に大きな影響を与えています。
これらの企業は、自社の強みと社会的ニーズを結びつけることで、パーパス経営を効果的に実現しています。
8-2: 業界別のアプローチの違い
「パーパス経営とは、業界の特性や社会的な役割に合わせて独自の存在意義を掲げる経営手法」です。そのため、業界ごとに異なるアプローチが見られます。
- 医療業界:医療業界では「患者の健康と安全を最優先にする」ことがパーパスの中心になります。そのため、最先端の治療法や医療機器の開発に重点を置き、治療の質を向上させることが重視されています。
- 金融業界:金融業界では、「人々の生活を安定させ、豊かにする」がパーパスとして掲げられることが多いです。このため、透明性のある金融商品や、地域社会を支援するローンなど、信頼性と公正性が強調された商品開発が行われています。
- ファッション業界:ファッション業界では「サステナビリティ」が重視され、エシカルファッション(環境や人権に配慮したファッション)の促進が進んでいます。リサイクル素材の利用や労働環境の改善がパーパスに基づく主要なアプローチとなっています。
このように、パーパス経営のアプローチは、各業界の特性や顧客ニーズに応じて異なります。パーパス経営が企業の価値向上につながるためには、自社の業界や顧客層に合わせた独自のパーパス設定が重要です。
8-3: 学ぶべきトレンドと手法
「パーパス経営とは、社会と共に成長を目指す経営手法」であり、各業界で採用されているトレンドや手法から学ぶべきことが多くあります。ここでは、今注目されているトレンドと、実践に役立つ手法をいくつかご紹介します。
- トレンド1: サステナビリティへの注力
サステナビリティ(持続可能性)は多くの業界で共通して見られるトレンドです。企業は環境に配慮した製品開発や、持続可能な素材の使用を増やすことで、社会にとって意義のある活動を行っています。 - トレンド2: 社会貢献型のビジネスモデル
「Bコープ認証」など、社会的な貢献を重視するビジネスモデルが注目されています。Bコープ認証は、社会や環境に与える影響を考慮した企業に与えられる認証で、多くの企業がこの認証を目指すことで、パーパス経営の信頼性を高めています。 - 手法1: ステークホルダーの参加
企業が掲げるパーパスを効果的に実行するためには、従業員や顧客、地域社会など、ステークホルダーの参加が欠かせません。ワークショップやアンケートを活用し、パーパスに対する意見を集め、経営に反映する手法が有効です。 - 手法2: パーパスに基づいたKPI(重要業績評価指標)の設定
パーパス経営の成果を測るため、KPIを設定し、定期的に効果を評価することが推奨されます。たとえば、環境への貢献度や顧客満足度など、パーパスに直接関連する指標をKPIとして定め、パーパス経営がしっかり機能しているかを確認する方法です。
こうしたトレンドや手法を活用することで、パーパス経営が企業に定着し、社会的な価値を提供しながら成長を目指すことが可能になります。
9: パーパス経営を支えるステークホルダー

パーパス経営を成功させるためには、企業が掲げるパーパスに共感し、それを支えてくれる多くのステークホルダーの存在が重要です。ステークホルダーとは、企業に直接または間接的に関わる人々のことで、特に従業員、顧客、投資家がパーパス経営の実現において大きな役割を果たしています。
ここでは、各ステークホルダーの役割とその関係構築の重要性について解説します。
9-1: 従業員とその役割
「パーパス経営とは、企業の存在意義を基盤にした経営」であり、従業員はその存在意義を実現する上で最も重要な役割を担っています。従業員がパーパスに共感し、そのパーパスに基づいて行動することで、企業のパーパスは実際の活動に反映され、具体的な成果につながります。
従業員がパーパス経営に貢献するためには、まず企業がパーパスを明確にし、それを従業員全員に浸透させることが重要です。パーパスを共有することで、従業員が日々の仕事に誇りを感じ、自分の役割が企業や社会にどのように貢献しているかを理解できるようになります。
さらに、従業員のアイデアや意見を取り入れることで、彼らが主体的にパーパス実現に向けて行動する環境を整えることも、パーパス経営を成功させるための鍵となります。
9-2: 顧客との関係構築
「パーパス経営とは、企業が顧客にどのような価値を提供するかを重視する経営手法」とも言えます。そのため、顧客もまた、パーパス経営において重要なステークホルダーのひとつです。企業が掲げるパーパスに共感する顧客が増えれば、ブランドへの信頼が深まり、長期的なファンを獲得することができます。
パーパスを軸にした関係構築の方法としては、まず企業が自社のパーパスや活動を透明性を持って顧客に伝えることが重要です。たとえば、環境に配慮した商品を提供する企業であれば、その取り組み内容や効果について情報を公開し、顧客に共感を呼びかけます。これにより、企業と顧客が価値観を共有し、信頼関係が築かれるのです。
また、顧客からのフィードバックを積極的に取り入れることで、企業のパーパスがさらに洗練され、顧客との関係が深まります。顧客が企業に期待する価値や方向性を把握するためのアンケートやレビューを活用することも、パーパス経営の効果を高める手段です。
9-3: 投資家の期待と関心
パーパス経営とは、長期的な視点で企業価値を向上させる経営スタイルでもあります。このため、企業の将来に投資する投資家もまた、重要なステークホルダーです。近年、投資家の多くは企業の財務状況だけでなく、パーパスに基づく社会的な貢献度や持続可能性に関心を寄せています。
投資家との関係を築くためには、企業が掲げるパーパスが具体的な活動や成果に結びついていることを示すことが大切です。たとえば、環境に配慮した活動や地域社会への貢献など、社会的な影響を数値化した報告を行うことで、投資家に対して企業の将来性と信頼性をアピールできます。また、持続可能な成長を目指す姿勢を示すことで、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を行う投資家からの支持を得やすくなります。
このように、投資家がパーパスに共感し、企業の成長を支援してくれることで、企業は財務的な安定を得ながらパーパス経営を続けることができます。
10: まとめ

「パーパス経営とは、企業が利益追求だけでなく、存在意義や社会的価値に基づいて経営を行うこと」です。この経営スタイルは、企業が社会や顧客、従業員に対してどのように貢献できるかを明確にすることで、持続可能な成長を目指します。現代では、消費者や投資家が企業の社会的な取り組みに注目しているため、パーパス経営は企業の競争力や信頼性を高める重要な要素となっています。
パーパス経営を導入することで、企業は競争力を向上させ、従業員のモチベーションを高め、顧客との強い信頼関係を築くことができます。
しかし、パーパスを単なるスローガンにするのではなく、具体的な活動や業務に反映させ、評価と効果測定を行うことが成功の鍵です。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用することで、パーパス経営がより効率的かつ広範に実現できるようになります。
さらに、従業員、顧客、投資家といったステークホルダーが企業のパーパスを支える役割を果たし、企業の存在意義に共感していることが、パーパス経営を成功に導きます。それぞれのステークホルダーとの関係を強化することで、企業は社会に対してポジティブな影響を与え、信頼と支持を得ながら成長することが可能です。
「パーパス経営とは」企業の未来を形づくる重要な経営手法であり、今後も多くの企業にとって不可欠な要素として広がっていくでしょう。企業が存在意義を明確にし、それを社会に示すことで、持続可能な未来を築くことができるのです。
パーパス経営を効果的に実現するためには、企業の価値観やナレッジを社員一人ひとりに浸透させ、理解の定着を図ることが重要です。
しかし、これを日常業務で継続的に行うのは簡単ではありません。ここで役立つのが、kokoroeです。
kokoroeは、社員に求められる知識を「毎日5分の反復テスト」で習慣的に定着させる教育サービスです。企業理念や業界知識、コンプライアンスなどの「ナレッジ」を社員に無理なく伝え続けることで、全員が共通認識を持ち、パーパス経営の実現を支えます。
kokoroeの継続的な学習で、記事で述べたような知識の定着と共通理解を深め、組織全体の成長に貢献できるでしょう。