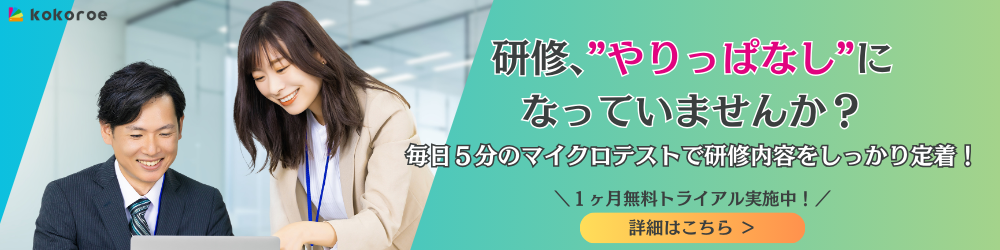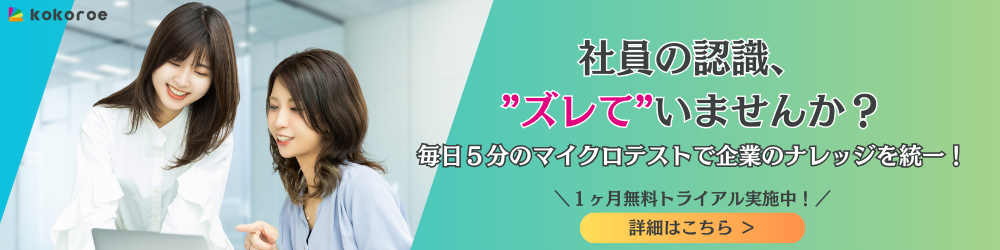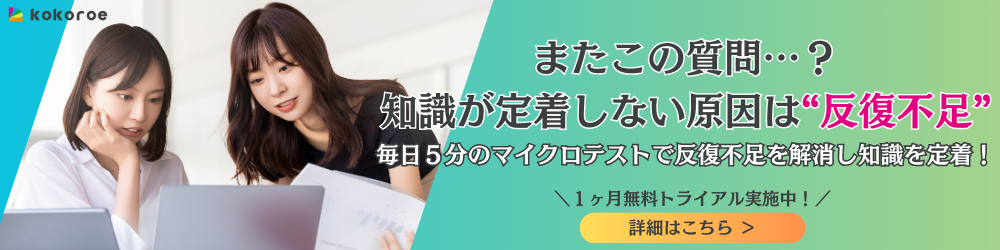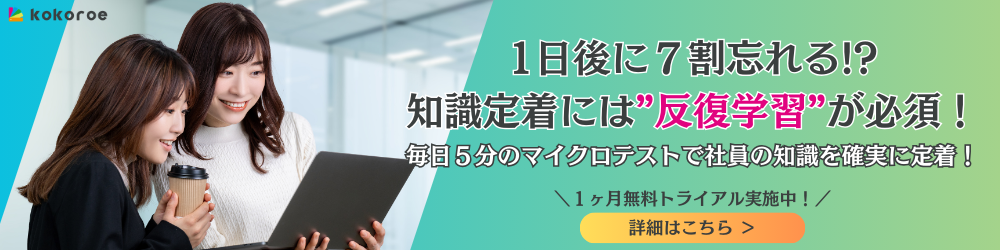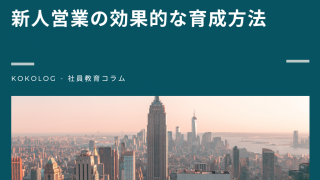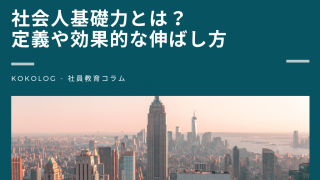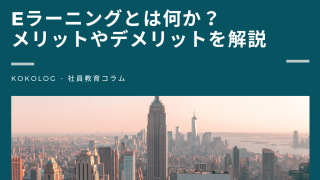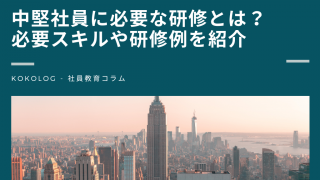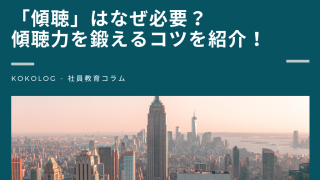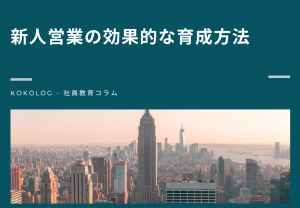即戦力採用を成功させる秘訣とは?選考から入社後のポイントを解説!
即戦力になることを期待して中途採用を行う企業は多いですが、必ずしも中途人材が即戦力になるわけではないという現実があります。前職で優れた成果を上げている中途人材が、なぜ自社で同じような成果を上げることができないのか?と疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。
当記事では、中途人材が即戦力として成果を上げることの難しさも踏まえたうえで、どのように中途採用を行い、また即戦力化していくかについて解説していきます。
中途採用が上手くいっていない、中途採用した人材が戦力化していないとお悩みであれば、ぜひご覧ください。
中途採用が「即戦力」になれない理由

中途採用の人材は、一般的には「即戦力性」が求められます。
しかし、結果的に期待通りの活躍ができていない人材が多いのも事実です。いったいなぜ、このような事態が起こってしまうのでしょうか。
まずは、中途採用社員の「即戦力化」が難しい理由について解説します。
中途採用が「即戦力」になれない理由
職種経験や場合によっては業界経験もある中途採用の社員が即戦力になれない理由として、「組織社会化」という大きな壁があることを理解しておく必要があります。
「組織社会化」とは、聞きなれない言葉かもしれませんが、「組織に加入した人が組織に馴染んで力を発揮するために必要な基礎知識を身に付けるプロセス」を指します。
ここでいう「基礎知識」とは、例えば以下のような内容を指します。
・企業理念やビジョン等の共通認識
・会社(組織)の歴史、組織体制や意思決定のプロセス
・バリューや行動規範等の価値観
・組織を構成する人
・社内用語や社内ツールの理解
スキルや経験を持った中途人材の即戦力化に失敗するケースでは、組織社会化が上手くできていないというパターンが多々見られます。
中途採用に成功している企業では、中途採用後の受け入れプロセスとして、組織社会化をスムーズにおこなうためのプロセスが組まれていることが殆どです。
入社人材の適応力と企業の受け入れ力
「組織社会化」をスムーズにおこなうために重要なカギとなるのは、「中途人材の適応力」と「企業の受け入れ力」です。
中途人材は、前職でのやり方や成功体験に固執せずに、新しい職場でのやり方を受け入れる必要があります。また、企業側は中途人材が力を存分に発揮できるように、一連のサポート体制を整えなくてはなりません。
例えば、配属部門を中心とした、他部門を含む業務レクチャーや歓迎会、ビジョンや組織の共有、社内用語集の作成、状況確認のための面談等が挙げられます。
即戦力採用を成功させる3つのポイント

素晴らしい経験や優秀なスキルを持った中途人材であっても、即戦力化するためにはきちんとプロセスを踏む必要があるということを確認した上で、中途採用における「即戦力採用」を成功させるためのポイントを解説していきます。
①活躍に必要な要素を明確にする
最初に押さえておきたいのは、該当職種で戦力になるためにはどのような特性やスキルが必要なのかを明確にしておくことです。具体的に採用活動の中で意識したい点は次の2つです。
(1)自社の募集職種で活躍するために必要なスキルや特性
例えば、同じ営業職でも会社によって活躍するために必要なスキルは大きく異なってきます。そのため、必要なスキルや要素は「営業経験」等の抽象的なものではなく、なるべく具体的なレベルまで分解しましょう。
(2)組織社会化の視点で自社と候補者の前職での働き方を比較する
必ずしもすべてが自社と一致している必要はありません。
ただし、採用から入社時まで、「即戦力化」を意識したうえで、『〇〇は前職と同じ感覚で働けるけど、〇〇はギャップを感じるかもしれません』ということを、あらかじめきちんと伝えることが結果的に即戦力化へと繋がります。
②配属部門の社員に採用へ関わってもらう
2つ目のポイントは、配属部門の社員を採用に関わらせることです。これは当たり前におこなわれているという企業も多いかもしれません。
配属部門の社員、とくに採用する候補者の上司となるマネージャークラスに関わってもらうことは非常に重要です。現場で必要としているスキルや特性を踏まえた採用をおこなうという目的に加え、採用市場の現状を現場社員に理解してもらう意味もあります。
また、配属部門の社員に面接や面談に参加してもらうことで、候補者が現場の雰囲気を知ることができ、組織社会化の入り口になるというメリットもあります。
③オンボーディングを実施する
3つ目のポイントは、即戦力化に向けたオンボーディングを導入することです。
日本企業では、新卒採用では非常に丁寧に新入社員研修をおこないますが、中途採用では殆ど研修をおこなわずに現場配属、OJTに入ってしまうケースがめずらしくありません。
時期も経験値もバラバラで入ってくる中途社員の研修が、OJTでの研修中心になるのはやむを得ないのですが、その中でも「組織社会化」を意識した受け入れプログラムを設計することが重要です。
また、OJTの中では、「自社での仕事の進め方の習得」と「自社に合わないような前職での仕事の進め方の廃棄」をOJT指導者がちゃんとアドバイスすることが重要です。
このとき、的確な助言をおこなえるようにするためにも、採用段階において自社の仕事の進め方と候補者がこれまでにおこなってきた仕事の進め方との違いを明確にしておくことがカギとなります。
中途採用で即戦力かどうかを見極める面接のポイント

最後に、中途採用の面接時に「即戦力となり得るか否か」を見極めるポイントについて解説します。
実績だけではなくエピソードの中身を確認する
採用面接において、自分を良く見せようという心理が働くのは当たり前のことです。
また、実績の数値がどれだけ良かったとしても、自社でも同じような数値を残してくれるとは限りません。
さらに、実績は必ずしも求職者の営業力やスキルによって得られたものとは限らず、他のメンバーの功績が大きかったり、たまたま商材・サービスが市場のニーズに合致していたりしたケースもあります。
このような落とし穴を防ぎ、候補者の力量をちゃんと把握するためには、構造面接の最も基本的な手法である「STAR面接」の手法を使って、エピソードの中身を確認することが大切です。
STAR面接とは、行動面接の一種で、限られた時間の中で求職者の本質に迫ることができる手法です。
STAR面接
・S(Situation:状況)
・T(Task:課題)
・A(Action:行動)
・R(Result:結果)
具体的には、候補者が「どのような状況で」「どのような業務を任され」「どのように行動し」「どのような成果を上げたのか」をひとつずつ、事実ベースの情報や意思決定プロセス等も含めて確認していきます。
これにより、状況における候補者の役割や立場、意思決定への関わり方を把握することができます。他にも、意思決定の傾向、周囲とのコミュニケーション等のコンピテンシーや性格特性をしっかり確認することで、候補者の人物像をしっかりと見抜くことができます。
面接だけではなくワークサンプルを実施する
ワークサンプルを実施すると、業務スキルを最も高精度で見極めることができます。
ワークサンプルとは、候補者に実際の業務に近い内容の仕事をさせて、その成果を採用評価の判断材料とする非常に効果的な手法です。
例えば、営業職の経験者であれば前職の商品・サービスで商談のロールプレイングをしてもらう、広報やマーケティング職の経験者であれば、自社の製品もしくは、ある商品・サービスを想定して、潜在顧客への認知、購入までの一連の流れを企画しプレゼンさせることで、実務的なスキルを推し量ることができます。
まとめ

中途採用でなるべく「即戦力採用」を実現するためのポイントは、以下の2点です。
①組織社会化のサポート
②募集業務にマッチした人材の採用
まず、見落とされがちなのが入社後のサポートです。
日本企業における中途採用の受け入れは、新卒と比べるとまだまだ未成熟です。組織社会化の要素を知ったうえで、オンボーディングのプログラムを組むだけで、採用後の即戦力化スピードがぐっと速まるでしょう。
また、募集業務にマッチした即戦力に近い人材の採用するうえでは、自社で活躍するために必要なスキルや特性を明確化し、人事だけでなく現場社員も採用に関わることで、より実践的な視点での判断ができるようにすることが重要です。