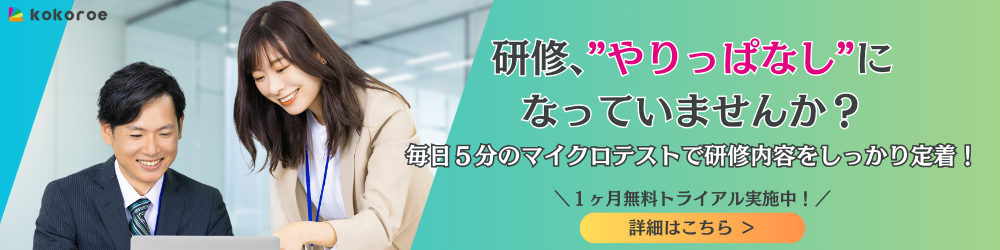ジョブクラフティングで変わる社員の働き方!導入メリットと成功ステップを徹底解説
社員のやる気が続かない、早期離職が多い、働き方改革がうまく進まない——。
こうした課題に直面している企業の人事・教育担当者の方に、いま注目されているのが「ジョブクラフティング」です。
ジョブクラフティングとは、社員が自らの仕事を再定義し、意味や価値を見出しながら、より主体的に働くことを促すアプローチです。単なる業務改善にとどまらず、エンゲージメント向上・離職防止・生産性アップなど、組織全体に好影響をもたらす革新的な手法として、多くの企業で導入が進んでいます。
本記事では、ジョブクラフティングの基本的な考え方から、企業にとってのメリット、導入のステップ、実際の成功事例、そして導入時の注意点までを網羅的に解説します。
社員の自律性を引き出し、組織の成長を後押しする新しい人材戦略をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1: ジョブクラフティングとは?

従来のように「会社から与えられた業務をそのまま遂行する働き方」では、社員のモチベーションやエンゲージメントを維持することが難しくなってきました。そうした背景の中で注目されているのが**「ジョブクラフティング(Job Crafting)」**です。
ジョブクラフティングとは、社員自らが自分の仕事を再設計し、より意味や価値を見出すことで、主体的かつ意欲的に働ける状態をつくるアプローチです。社員一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、組織全体の活性化にもつながるこの手法は、企業の人事・教育戦略において大きな注目を集めています。
1-1: ジョブクラフティングの定義と基本概念
「ジョブクラフティング」とは、2001年にアメリカの組織心理学者ジェーン・ダットン氏らが提唱した概念です。日本語に訳すと「仕事の再構築」や「仕事の作り直し」となります。
社員自身が、以下の3つの側面から自分の仕事を能動的に変えていくことがジョブクラフティングの基本です。
- タスク・クラフティング(Task Crafting): 業務の内容や進め方を工夫する
- リレーションシップ・クラフティング(Relationship Crafting): 関わる人間関係を見直す
- コグニティブ・クラフティング(Cognitive Crafting): 仕事の捉え方や意味付けを変える
このように、社員が自ら仕事に対して主体的に関与することで、働くことへの納得感や目的意識が高まり、やる気や成果にも良い影響を与えるとされています。
1-2: なぜ今ジョブクラフティングが注目されているのか
ジョブクラフティングが注目される背景には、以下のような働き方の変化や人材マネジメントの課題があります。
- 離職率の上昇とエンゲージメントの低下
近年、多くの企業が「若手社員の早期離職」や「やる気の低下」といった課題に直面しています。画一的な業務分担では、個人の成長意欲を満たしきれず、ミスマッチが生まれやすくなっています。 - 働き方の多様化とキャリア自律の必要性
リモートワークや副業解禁など、働き方の選択肢が広がる中で、社員一人ひとりが自分のキャリアに責任を持つ「キャリア自律」が求められています。ジョブクラフティングは、その実現を後押しする手段でもあります。 - 組織の柔軟性とイノベーション力の向上
環境変化の激しい時代においては、現場で柔軟に動ける社員が企業の競争力に直結します。社員が自ら工夫し、変化を起こしていくジョブクラフティングの考え方は、まさに現代の企業に必要なマインドセットといえます。
1-3: 他の人材開発アプローチとの違い
人材開発の手法はさまざまありますが、ジョブクラフティングが特にユニークなのは、**「社員自らが主体となる点」**です。
たとえば、
- OJT(On the Job Training): 上司や先輩が業務を通じて教育するスタイル
- 研修・eラーニング: 教える側が設計した内容を受け身で学ぶ形式
- 目標管理制度(MBO): 会社が設定した目標をベースに成果を測る
といった従来のアプローチでは、**「与えられることが前提」**になっていることが多いのに対し、
ジョブクラフティングは、社員自身が仕事をどう変えるかを考え、実行に移すという、より自律的な姿勢を促す点が特徴です。
この自律性こそが、社員の「内発的動機づけ」を高め、持続的な成長や組織への貢献につながる要因となっています。
この後のセクションでは、ジョブクラフティングが企業にもたらす具体的なメリットや、導入方法、実践事例などを詳しく解説していきます。
**「社員の主体性を高めたい」「働き方改革を進めたい」**とお考えの人事・教育担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
2: ジョブクラフティングが企業にもたらすメリット

ジョブクラフティングは、社員一人ひとりが自らの業務に意味を見出し、仕事への関与度を高めるアプローチです。単に社員の意欲を高めるだけではなく、組織全体にも好影響を与える数多くのメリットがあります。
ここでは、企業視点でとくに重要な「モチベーション・エンゲージメントの向上」「離職率の低下」「生産性と創造性の向上」という3つの観点から、ジョブクラフティングの具体的な効果を解説します。
2-1: 社員のモチベーションとエンゲージメント向上
社員が自らの仕事を主体的に捉え直し、自分らしく再設計することで、仕事に対する納得感や達成感が大きく向上します。これにより、外部からの評価や報酬ではなく、内発的なモチベーションが引き出されるのが、ジョブクラフティングの最大の強みです。
また、自ら工夫しながら仕事に取り組むことで、**「自分の仕事が組織にどう貢献しているか」**を実感しやすくなり、組織との心理的なつながり=エンゲージメントの向上にもつながります。
たとえば、日常業務に工夫を加えたり、社内の関係性を自ら築いたりすることで、社員が「自分らしく働いている」という感覚を持つようになり、結果的に仕事への意欲や継続性が高まります。
2-2: 離職率の低下と定着率の改善
ジョブクラフティングは、社員が自分のキャリアに対する主導権を持てる環境づくりを支援します。
「自分の強みを活かせる」「成長実感がある」と感じられる職場では、社員の満足度が高まり、早期離職やモチベーションの低下を防ぐことが可能になります。
とくに若手社員や中堅層においては、「このままでいいのか」「自分に合っているのか」という迷いが離職の大きな要因になりますが、ジョブクラフティングによって自身の役割を能動的に再構築できるようになると、その不安が軽減され、長期的な定着につながります。
また、社員が自分で仕事を創り出す風土が根付けば、企業文化としても自律的な働き方が定着し、人事施策全体の効果も高まります。
2-3: 生産性と創造性の向上
自分の業務に創意工夫を加えながら取り組むことで、社員はより効率的で成果の出る方法を自然と模索するようになります。その結果、業務プロセスの改善や無駄の削減が進み、生産性が向上します。
また、ジョブクラフティングでは、社員が日々の業務に対して新しい視点や関わり方を試みるため、創造性(クリエイティビティ)も育まれやすくなります。自ら仕事を「意味あるもの」に変える過程で、社内の既存の枠にとらわれない発想や、新たな連携・アイデアが生まれることも少なくありません。
こうした動きは、結果的にイノベーションの種となり、現場主導の改善や新しい価値の創出を可能にします。これにより、単なる個人のパフォーマンス向上にとどまらず、組織全体の競争力強化にも直結していきます。
次のセクションでは、ジョブクラフティングをどのように企業へ導入していくのか、その具体的なステップを詳しく解説します。
**「やってみたいが、どう始めればよいか分からない」**という人事・教育担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
3: ジョブクラフティングの導入ステップ

ジョブクラフティングは、社員が主体的に仕事を捉え直し、やりがいや意味を再発見するための強力なアプローチです。
しかし、いきなり現場任せで導入してもうまく機能しないケースも少なくありません。
企業としてジョブクラフティングを効果的に根付かせるには、人事部門が戦略的に設計した導入ステップを踏むことが不可欠です。
ここでは、導入における3つの基本ステップ
「①現状把握と課題分析 → ②理解促進と研修 → ③実践支援とフィードバック体制」
について、順を追って解説します。
3-1: 現状把握と課題分析
まず取り組むべきは、自社の人材育成や組織風土に関する現状の把握と課題の特定です。
以下のような視点から社内の現状を可視化することで、ジョブクラフティング導入の方向性が明確になります。
- 社員のエンゲージメントは高いか?
- 業務にやりがいを感じているか?
- 主体性の発揮や自律的な行動が求められているか?
- 現場のマネージャーやリーダー層が変化を受け入れやすい風土か?
このフェーズでは、社内アンケートや1on1面談、退職者インタビューなどを活用し、社員の声を丁寧に拾うことが成功のカギです。課題が明確になれば、ジョブクラフティングをどの部署から導入すべきか、どのようなテーマで取り組むべきかの判断材料にもなります。
3-2: 社員への理解促進と研修の実施
ジョブクラフティングを企業文化として根付かせるためには、社員一人ひとりの理解と納得感が不可欠です。
そのための第一歩が、ジョブクラフティングの目的・メリットを伝える研修やワークショップの実施です。
具体的には以下のようなアプローチが有効です。
- 講義形式でジョブクラフティングの基礎を学ぶ
- ワークを通じて自身の業務を「見える化」し、再設計する体験を提供
- グループディスカッションで他者視点からの気づきを得る
また、マネージャー層への理解促進も重要です。
彼らがジョブクラフティングを「勝手な仕事の再定義」と誤解してしまうと、現場での実践にブレーキがかかってしまいます。
管理職向けの説明会やフォローアップセッションもセットで行うことをおすすめします。
3-3: 実践支援と継続的なフィードバック体制の構築
社員にジョブクラフティングの考え方を浸透させたあとは、日常業務の中で実践できる仕組みづくりがポイントになります。
たとえば、
- ジョブクラフティングをテーマにした定期的な1on1の実施
- 業務改善提案制度や社内公募制度との連動
- 社内SNSやイントラネットでの「成功事例」の共有
- ジョブクラフティングに取り組んだ社員へのポジティブなフィードバック
といった支援策を組み合わせることで、社員は安心して主体的な取り組みを続けやすくなります。
また、人事部門としては、導入後の効果測定やフィードバックも重要です。
「エンゲージメントスコアの推移」や「離職率の変化」「業務改善数」など、KPIを定めて成果を可視化し、経営層にも定期報告することで、全社的な取り組みへと広げやすくなります。
次のセクションでは、実際にジョブクラフティングを導入し、成果を上げている企業の事例をご紹介します。
導入に不安のある人事・教育担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
4: 実践企業の成功事例

ジョブクラフティングは理論上の概念だけでなく、実際の企業でもさまざまな形で導入され、成果を上げています。
ここでは、「中小企業」「大企業」「部署単位でのスモールスタート」という3つのタイプに分けて、現場での実践事例をご紹介します。自社に合った導入方法をイメージするうえで、ぜひ参考にしてください。
4-1: 中小企業における活用例
ある製造業の中小企業(従業員数約80名)では、若手社員のモチベーション低下と離職が続いていたことから、ジョブクラフティングを導入しました。人事担当者がまず行ったのは、**月1回の「業務を語る会」**の開催。社員が日頃どのような仕事に取り組み、何を感じているかを共有する場を設けたのです。
この取り組みにより、社員同士が「仕事に対する捉え方」の違いを知り、自ら業務に意味を見出すきっかけが生まれました。
さらに、自分が得意な業務を中心に再配置できるような柔軟な業務調整も実施した結果、1年で離職率が30%から10%に改善。社員からは「会社に居場所があると感じるようになった」という声も寄せられました。
中小企業だからこそ、組織の変化が速く、社員との距離が近い分、ジョブクラフティングが浸透しやすい環境があったと言えるでしょう。
4-2: 大企業での人事施策との連携事例
国内の大手IT企業では、「キャリア自律支援」をテーマにジョブクラフティングを取り入れています。具体的には、年1回の自己申告制度と連動したジョブクラフティング研修を全社員に実施し、自分の業務の再定義を促すワークを組み込みました。
また、社員のキャリアビジョンに沿った「キャリアチャレンジ制度」も併用。自身がやりたい仕事やスキルアップしたい領域を申告し、異動や新規プロジェクト参画ができる仕組みを整備しています。
この結果、若手・中堅社員のエンゲージメントが大幅に改善。社内調査では「自分のキャリアに責任を持てるようになった」と感じる社員の割合が前年比で25%以上増加しました。
大企業においては、制度と連動した戦略的導入がジョブクラフティングの成果を引き出す鍵となります。
4-3: 部署単位でのスモールスタート成功例
ある金融系企業では、全社導入に先駆けて、営業部門の1チーム(約10名)でジョブクラフティングを試験的に導入しました。まず実施したのは、1on1ミーティングで「どんな仕事にやりがいを感じるか」を丁寧にヒアリングする取り組みです。
そこから得た情報をもとに、社員が希望する業務や強みを活かせる業務への再アサインを段階的に実施。あわせてチーム内での情報共有会や成功事例の共有を通じて、前向きな風土の醸成に努めました。
その結果、営業成績がチーム全体で前年比110%を記録。さらに、従業員満足度調査でも高評価を得るなど、定量・定性両面での成果が確認されました。
スモールスタートによって、失敗リスクを抑えながら有効性を検証できる点は、多くの企業で応用可能なアプローチです。
このように、企業の規模や組織構造に関わらず、ジョブクラフティングは柔軟にカスタマイズして導入することが可能です。
次章では、導入を進めるうえで人事が注意すべきポイントや、よくある課題について解説していきます。
5: 導入時の注意点とよくある課題

ジョブクラフティングは、社員の主体性を引き出すうえで非常に有効なアプローチですが、導入にあたってはいくつかの注意点や落とし穴があります。
とくに企業の人事・教育担当者にとっては、「放任との違い」「管理職の巻き込み」「評価との整合性」といった観点から、慎重に設計・運用していく必要があります。
ここでは、ジョブクラフティング導入時によく見られる課題とその対処法について、3つの視点で解説します。
5-1: 社員任せにしすぎるリスクと対処法
ジョブクラフティングは、社員の自主性を尊重するアプローチですが、「好き勝手に仕事を変えていい」と誤解されるリスクもあります。
この状態を放置すると、組織全体の方向性と一致しない行動や、業務の分担不均衡が生じる可能性があります。
対処法としては、以下のような**「ガイドラインの明確化」と「定期的な対話の場」**が効果的です。
- ジョブクラフティングの範囲・目的を明確に伝える
- 上司との1on1やチーム内ミーティングで「目的」と「期待する役割」のすり合わせを行う
- 社内ルールや成果指標と照らし合わせて、自由と責任のバランスを取る
ジョブクラフティングを単なる個人の自由に終わらせず、組織の成果と連動する仕組みにすることが重要です。
5-2: 管理職の理解と協力が不可欠な理由
ジョブクラフティングが現場でうまく機能するかどうかは、管理職の理解とサポートに大きく左右されます。
マネージャー層がこの考え方を正しく理解していない場合、「勝手に業務を変えられて困る」「管理が難しくなる」といった反発が生じる可能性があります。これが現場での実践を妨げ、社員の意欲を削ぐ結果にもつながりかねません。
そのため、人事部門としては以下のような働きかけが必要です。
- 管理職向け研修でジョブクラフティングの意義や期待される役割を共有する
- 管理職自身にもジョブクラフティングを実践してもらい、体感させる
- 現場で起きる変化に対して、伴走支援できる体制を整える
マネージャーが**「社員の挑戦を支援するパートナー」**として機能することで、組織全体に前向きな変化をもたらす土壌が整います。
5-3: 評価制度との整合性の取り方
ジョブクラフティングでは、社員が自発的に役割や仕事の進め方を工夫するため、従来の画一的な評価制度と乖離が生じるリスクがあります。
たとえば、次のような課題が想定されます。
- 業務範囲が柔軟になり、成果の定義があいまいになる
- イノベーションや改善行動が数値化しにくい
- 自主的な行動が評価に反映されず、不満が出る
これに対しては、成果だけでなくプロセスや挑戦姿勢も評価対象に含めることが重要です。具体的には、
- 「自己目標の設定」と「達成度の自己評価」の導入
- ジョブクラフティングによる改善提案数や社内貢献度の可視化
- 上司による定性的なフィードバックの充実
などを通じて、社員の主体的な取り組みを正当に評価することができます。
評価制度が変われば、社員も安心してジョブクラフティングに取り組めるようになり、組織のエンゲージメントと成果創出の両立が可能になります。
次のセクションでは、ジョブクラフティングを活かした人材育成の将来像について解説します。人材の自律と組織の成長をどう結びつけるかに関心のある方は、ぜひ引き続きご覧ください。
6: ジョブクラフティングを活かした人材育成の未来

変化が激しく、将来が見通しづらい時代において、企業に求められる人材育成は大きく変わりつつあります。従来のように「教える」「管理する」だけの育成では、環境変化に対応できる柔軟で自律的な人材は育ちにくくなっています。
そうした中で注目されるのが**「ジョブクラフティングを軸にした人材育成」**です。これは、社員一人ひとりが自ら考え、仕事の意味を再定義しながら成長していく新しいスタイルの育成アプローチです。
ここでは、ジョブクラフティングが人材育成の未来にどう貢献するかを、「自律型人材の育成」「キャリア支援との連動」「今後の人材戦略の位置づけ」という3つの観点から解説します。
6-1: 自律型人材の育成との相性
自律型人材とは、自ら考え、行動し、学び続ける人材のことです。組織に依存せず、自分の価値を見出しながら成果を上げていくこのタイプの人材は、VUCA時代の企業成長に不可欠な存在です。
ジョブクラフティングはまさに、こうした自律型人材の育成と非常に相性が良い手法です。
- 自分の仕事に目的や意味を見出す
- 得意・関心に基づいて役割を広げていく
- 現場での試行錯誤を通じて成長していく
といった一連のプロセスが、自己認知力・当事者意識・学習意欲を自然と高めてくれるからです。
また、従来の一斉型研修では届きにくかった「日常業務ベースの学び」が促進されるため、学びと実務が直結した実践的な人材育成が可能になります。
6-2: キャリア支援との連動可能性
近年、多くの企業で「キャリア自律支援」への取り組みが加速しています。社員が自らのキャリアを主体的に設計し、自律的に行動できるようにするための支援は、ジョブクラフティングとの親和性が高い領域です。
ジョブクラフティングでは、自分の価値観や強みをもとに仕事のあり方を考え直すプロセスを伴うため、キャリアビジョンと日々の仕事が結びつきやすくなります。
たとえば、
- キャリア面談での対話をベースにした業務アレンジ
- キャリア開発研修と組み合わせたジョブクラフティングワーク
- 異動希望制度や社内公募との連動による機会提供
といった施策により、社員が「今の仕事」と「将来の自分」を結びつけやすくなり、キャリアの納得感と持続性が高まります。
ジョブクラフティングは、短期的なパフォーマンスだけでなく、中長期的なキャリア形成を支援するツールとしても機能するのです。
6-3: 今後の人材戦略における位置づけ
ジョブクラフティングは、単なる育成施策の一つにとどまらず、組織全体の人材戦略を再設計するうえでの重要なコンセプトになりつつあります。
特に、以下のような課題を抱える企業にとっては、ジョブクラフティングの導入が戦略的な解決策となり得ます。
- 管理型から自律型への組織文化転換を進めたい
- リスキリングや越境学習をより実務と接続させたい
- 一人ひとりの能力を最大限に引き出す仕組みが欲しい
さらに、ジョブクラフティングは心理的安全性の醸成や、ダイバーシティ推進、エンゲージメント向上といった多面的な効果をもたらすため、従来の人事制度や育成体系に統合していくことで、組織全体の底上げにつながります。
これからの人材戦略においては、「どう評価するか」「何を教えるか」だけでなく、「社員がどう仕事を意味づけし、どんな成長を遂げたいか」を支援する視点が欠かせません。ジョブクラフティングは、まさにその視点を実現するキードライバーとなるのです。
次のセクションでは、これまでの内容を踏まえ、ジョブクラフティング導入によって得られる組織変革の全体像をまとめていきます。
導入を検討している方は、ぜひ最終章もご確認ください。
7: まとめ|ジョブクラフティングで主体的な働き方を実現しよう

ジョブクラフティングは、社員が自ら仕事の意味ややり方を見つめ直し、主体的に働くことを促す革新的な人材開発アプローチです。
業務の効率化や生産性の向上だけでなく、モチベーションの向上、エンゲージメントの強化、離職率の低下といった、組織全体にポジティブな変化をもたらします。
本記事では、以下のポイントを中心に解説しました。
- ジョブクラフティングの定義と注目される背景
- 導入によるメリットと効果(エンゲージメント・定着率・創造性向上など)
- 実際の導入ステップと成功事例
- 注意点と制度設計上のポイント
- 自律型人材育成やキャリア支援との連動性
現代の人材戦略においては、単にスキルを教えるだけでなく、「社員がどう働くか」「どのように成長するか」を自ら選び取れる環境の整備が重要になっています。
ジョブクラフティングは、その実現をサポートする強力な武器となるでしょう。
人事・教育担当者の皆様にとって、今こそ「ジョブクラフティングを軸にした育成・評価・制度設計」を再構築する絶好のタイミングです。
まずは小さな取り組みからでも、現場に新しい風を吹き込んでみてはいかがでしょうか。
社員の働き方が変われば、組織の未来もきっと変わります。
ジョブクラフティングを通じて、企業と社員がともに成長する持続可能な仕組みを築いていきましょう。
社員の主体性を引き出し、エンゲージメントや生産性を高める「ジョブクラフティング」は、企業にとって大きな可能性を秘めたアプローチです。しかし、せっかく社員が自らの仕事に意味を見出し、学び始めても、その知識が定着しなければ行動変容にはつながりません。
そこでおすすめしたいのが、**反復学習で知識を定着させるマイクロラーニングツール「kokoroe」**です。
「kokoroe」は、1日5分の反復テストを通じて、学んだ内容を確実に記憶に残し、**自律的な働き方を支える土台となる“ナレッジの定着”**を支援します。さらに、企業独自の内容に対応したテストの自動生成や、成果の可視化機能により、ジョブクラフティングの効果を最大限に引き出す仕組みが整っています。
社員の主体性×確かな知識の定着。この組み合わせこそが、真の人材育成と組織成長を実現します。
ジョブクラフティングを成功に導く「学びの仕組み」として、ぜひ「kokoroe」をご活用ください。