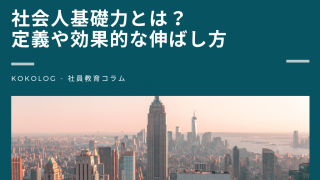「経験学習」とは?社員の成長を加速させる実践的な人材育成法を解説!
社員の成長を加速させるカギとして注目されている「経験学習」。実践を通じて学びを深めるこの手法は、知識の定着や自走人材の育成に大きな効果を発揮します。本記事では、経験学習の基本から導入のポイント、成功事例までをわかりやすく解説します。
1: 経験学習とは何か?その基本と注目される理由

人材育成の方法が多様化する中で、「経験学習」が改めて注目を集めています。従来の座学中心の研修だけではなく、**現場での経験を通じて社員が“自ら学び、成長していく”**この学習アプローチは、実務に直結し、成果にもつながる点が多くの企業で評価されています。
本章では、経験学習の基本的な考え方や、その注目の背景、他の学習手法との違いについて解説します。
1-1: 経験学習の定義と基本概念
「経験学習」とは、実際の経験を通じて学びを得るプロセスを指します。アメリカの教育学者デイビッド・コルブ(David Kolb)が提唱した「経験学習モデル(Kolb's Experiential Learning Cycle)」が広く知られており、次の4つのサイクルで構成されています。
- 具体的な経験(Concrete Experience)
- 内省的観察(Reflective Observation)
- 抽象的概念化(Abstract Conceptualization)
- 積極的実験(Active Experimentation)
このサイクルを回すことで、人は経験を単なる出来事で終わらせず、自らの行動や考え方を振り返り、新たな知識やスキルとして習得していきます。つまり、経験学習は単なる“経験”ではなく、**「経験を学びに変える仕組み」**なのです。
1-2: なぜ今、企業で経験学習が注目されているのか
近年、企業を取り巻く環境は急激に変化しています。テクノロジーの進化、働き方の多様化、そして人材の流動性の高まりにより、**従業員が自ら考え、行動し、成長する力=「自走力」**がますます求められています。
そこで注目されているのが「経験学習」です。理由は以下の通りです。
- 即戦力育成に直結する:現場の課題を通じて学ぶため、学習内容がすぐに実践につながる
- 主体的な学びを促す:教え込むのではなく、考えさせることで学習定着度が高まる
- リーダーシップや問題解決力の強化:経験を内省することで、より深い自己理解と行動変容を促進
さらに、若手人材の育成だけでなく、中堅・管理職のリーダーシップ開発にも有効であり、研修設計に経験学習を取り入れる企業が増加しています。
1-3: 経験学習と他の学習手法(集合研修・座学など)との違い
従来の人材育成手法と比較すると、経験学習には以下のような違いがあります。
| 学習手法 | 特徴 | 学習の深さ | 実務への応用度 |
| 座学・講義 | 知識を一方向でインプットする形式 | 浅い | 低い |
| 集合研修 | グループワークなどを通じた学び | 中程度 | 中程度 |
| 経験学習 | 実務の中で経験し、振り返りながら学ぶ | 深い | 高い |
つまり、経験学習は**“自ら行動し、考え、改善する”という学びのプロセス**を通じて、社員により深い理解と定着をもたらします。
特に、一方通行の知識伝達に限界を感じている企業や、実践力のある人材を育てたいと考える企業にとって、経験学習は極めて有効なアプローチと言えるでしょう。
次章では、この経験学習を体系的に理解するために不可欠な「コルブの経験学習サイクル」について、具体的な4ステップを解説します。
2: 経験学習サイクル(Kolbモデル)の4ステップ

社員の自律的な成長を支援するうえで欠かせないのが、「経験学習サイクル」と呼ばれる4つのステップです。
アメリカの教育学者デイビッド・コルブ(David Kolb)が提唱したこのモデルは、単なる経験を“学び”へと変えるための理論的フレームワークとして、多くの企業研修や教育現場で活用されています。
以下では、各ステップを人材育成の観点からわかりやすく解説していきます。
2-1: 第1ステップ:具体的な経験(Concrete Experience)
まず経験学習のスタート地点となるのが、**「具体的な経験」**です。これは、社員が実際に業務や課題に直面し、体験することを指します。
たとえば、以下のようなケースが該当します:
- クレーム対応や顧客提案などの実務体験
- チームリーダーとしてのプロジェクトマネジメント
- 社内会議でのファシリテーション経験
この段階では、成功体験も失敗体験もすべてが“学びの素材”となります。大切なのは、教科書的な知識では得られない「リアルな体験」を積むことです。
人事や教育担当者としては、社員がチャレンジできる環境や役割を意識的に設計することが求められます。
2-2: 第2ステップ:内省的観察(Reflective Observation)
次に重要なのが、「経験をそのままにせず、振り返ること」です。これが第2ステップの内省的観察です。
この段階では、以下のような問いかけが有効です:
- なぜそのような結果になったのか?
- どの場面で何を感じ、どう判断したのか?
- 他のやり方があったのではないか?
この振り返りを通じて、社員は単なる出来事から意味を見出し、自分自身の行動や思考パターンに気づくことができます。
ここでポイントになるのが、安全に内省できる環境づくりです。メンターや上司によるフィードバックの場や、チームでの振り返りセッションが有効です。
2-3: 第3ステップ:抽象的概念化(Abstract Conceptualization)
内省によって得られた気づきを、「一般化された学び」へと昇華させるのが、このステップです。
たとえば、こんな形で概念化されます:
- 「相手の立場を想像して伝えると、説得力が上がる」
- 「準備不足がトラブルを招くので、事前確認は必須」
- 「部下が主体的に動けるよう、任せる姿勢が必要」
このプロセスを経ることで、社員は個別の経験から汎用的なスキルや原則を導き出すことができます。
この段階では、研修資料やフレームワークの活用も有効で、実体験を理論と結びつける支援が人事側に求められます。
2-4: 第4ステップ:積極的実験(Active Experimentation)
最後に重要なのが、「次はこうしてみよう」と新たな行動にチャレンジするステップです。これが積極的実験です。
ここでは、以下のような姿勢が促されます:
- 新たな伝え方でプレゼンに挑戦する
- 前回の失敗を踏まえた段取りで会議を進行する
- チームメンバーへの関わり方を変えてみる
この実験によって新たな経験が生まれ、再びサイクルが回り始めます。つまり、経験学習は一度きりではなく、繰り返し回すことで効果が高まる循環型の学習プロセスなのです。
このサイクルを業務や研修に組み込むことで、社員は学び続ける力=ラーニングアジリティを自然に身につけていきます。
次章では、この経験学習サイクルをいかに企業の人材育成に活かすか、具体的な活用法や設計ポイントをご紹介します。
3: 経験学習を人材育成に活かす方法

経験学習は、単なる理論にとどまらず、日々の業務や研修現場で“実践的に活用できる”学習手法です。特に、OJTや研修、フィードバックの設計に取り入れることで、社員の主体性・実行力・課題解決力を高めることが可能です。
ここでは、企業の人材育成において経験学習を効果的に活かすための具体的な方法をご紹介します。
3-1: OJTとの相性と組み合わせ方
経験学習と最も相性が良い施策のひとつが、**OJT(On the Job Training)**です。OJTは、社員が実際の業務を通じてスキルを習得する仕組みであり、「具体的な経験」を提供する場として最適です。
しかし、ただ“やらせる”だけでは経験学習は成立しません。重要なのは、以下の要素をOJTに組み込むことです:
- 振り返りの時間を設ける(内省)
→ 実施後に、本人と指導者で「なにがうまくいったか」「なにが課題だったか」を対話 - 仮説を立てて再チャレンジする(積極的実験)
→ 次回はどう工夫するかを言語化し、計画させる - 学びを言語化させる(概念化)
→ 形式知化することで再現性のあるスキルへ変換
このように、OJTに経験学習サイクルの4ステップを意識的に組み込むことで、単なる作業経験が**“成長につながる学びのプロセス”**へと変わります。
3-2: 社内研修・ワークショップでの活用事例
社内研修やワークショップにおいても、経験学習の考え方を取り入れることで、参加者の学習効果を高めることができます。
例えば以下のような設計が効果的です:
- ロールプレイの導入(具体的な経験)
→ 営業研修での顧客対応シーン、マネジメント研修での部下指導シーンなど - グループディスカッション(内省)
→ 体験を共有し、他者視点での気づきを得る - フレームワークや原則の紹介(概念化)
→ 経験を理論的に整理する - 次回の業務への適用計画(実験)
→ 実務に活かすアクションプランを作成
このように、単なる知識伝達に終わらせず、「体験→振り返り→応用」へとつなげる流れを設計することで、研修効果は格段に向上します。
3-3: 上司・メンターによるフィードバックの重要性
経験学習を成立させるうえで欠かせないのが、上司やメンターからのフィードバックです。
社員自身が経験を振り返るだけでは気づけないポイントに気づかせ、学びを深めるための“外部からの視点”が重要です。
効果的なフィードバックのポイントは以下の通りです:
- 観察に基づく具体的なコメント
→ 「◯◯の時、相手の反応はどうだった?」「□□の説明がわかりやすかった」など - 質問による内省の促進
→ 「次はどうしてみたい?」「何を改善すれば成果が変わりそう?」 - 安心して失敗を話せる関係性の構築
→ 否定せず、失敗を“学びのチャンス”と捉える文化づくり
このように、日常的な関わりの中で経験学習のサイクルを回す支援をすることで、部下や若手社員は成長実感を得やすくなります。
人事や教育担当者としては、フィードバック力の高い管理職やメンターを育成する施策も同時に検討することが大切です。
次章では、経験学習の導入によって得られるメリットや、実際の企業が得た成果について、より具体的に解説していきます。
4: 経験学習を導入するメリットと効果

経験学習は、単なる理論学習にとどまらず、実際の行動や業務の中で学びを深めることで、社員一人ひとりの成長を加速させる強力な人材育成手法です。企業の教育現場においても、OJTや研修に経験学習を取り入れることで、従業員の学びの質が大きく向上します。
ここでは、経験学習を導入することで得られる具体的なメリットと効果について解説します。
4-1: 自ら考え、行動する“自走人材”の育成
人事や教育担当者にとって、自ら考え、行動し、成果を出せる“自走人材”の育成は永遠のテーマと言えます。その点で、経験学習は非常に有効です。
経験学習では、社員が自ら体験を振り返り、気づきを得て、次の行動につなげていきます。この一連のプロセスを繰り返すことで、次第に以下のような力が養われます:
- 状況に応じた判断力
- 問題を発見し、解決策を考える力
- 自分で学ぶ意欲と方法論(メタ認知力)
これらはまさに、現場で“自律的に動ける”人材の特徴です。知識やスキルだけでなく、「考え方」や「姿勢」が身につくのが、経験学習の大きな魅力と言えるでしょう。
4-2: 理解から定着・実践へつながる深い学び
従来の研修では、知識のインプットに偏り、受講後に「わかったつもり」で終わってしまうことも少なくありません。しかし、経験学習では、体験→内省→概念化→実践というプロセスを経るため、学びが深く定着します。
たとえば、マネジメント研修において理論だけでなく、
- 自身のマネジメント失敗体験の振り返り
- フィードバックのロールプレイ
- 翌週の会議での実践計画の立案
といった一連の流れを取り入れることで、「使える学び」に変わります。
つまり、経験学習は**“行動変容”を伴う学習プロセス**であり、研修効果の最大化に直結する手法です。定着率の高い研修を目指す企業にとって、極めて有効なアプローチです。
4-3: 若手・管理職それぞれにおける育成効果
経験学習は、階層や役割を問わず活用できる点も大きな特徴です。若手社員から管理職まで、それぞれの成長ステージに応じた学びを提供できます。
■ 若手社員の場合
入社間もない若手社員には、まず「経験の機会」が必要です。業務を通じた実践と、上司やメンターによる振り返りの機会をセットにすることで、主体性や問題解決力が早期に育成されます。結果として、早期離職防止や早期戦力化にもつながります。
■ 管理職の場合
一方、管理職には過去の成功体験にとらわれず、環境変化に柔軟に対応する力が求められます。経験学習を通じて、部下との関わり方や意思決定の振り返りを行うことで、リーダーシップの質やマネジメント力の向上が期待できます。
このように、経験学習は一過性の研修ではなく、継続的な成長を支える土台として、多くの企業で導入が進んでいます。
次章では、実際に経験学習を導入し、効果を上げている企業の事例を通じて、導入のヒントや成功のポイントを探っていきます。
5: 経験学習を定着させるための実践ポイント

経験学習は非常に効果的な人材育成手法ですが、導入するだけで自然と定着するものではありません。
社員一人ひとりが「経験から学び続ける姿勢」を身につけるためには、環境設計や仕組み化が不可欠です。
ここでは、企業が経験学習を現場に根付かせるために実践できるポイントを3つの観点から紹介します。
5-1: 経験を「学び」に変える問いかけの設計
経験学習の核となるのは「振り返り」です。
しかし、ただ「どうだった?」と聞くだけでは表面的な感想で終わってしまい、本質的な学びにはつながりません。そこで重要なのが、**学びを引き出す“問いかけの質”**です。
効果的な問いかけの例は以下の通りです:
- 「なぜその判断をしたのか?」(思考プロセスの可視化)
- 「どこに難しさを感じたか?それをどう乗り越えたか?」(課題と対応)
- 「次はどうアプローチしたいか?」(再挑戦への意識づけ)
こうした問いを通じて、社員自身が内省しやすくなり、“なんとなくの経験”が“再現性のある学び”へと変わっていきます。
人事や教育担当者は、上司やメンターがこうした問いかけを行えるように、問いのガイドやフィードバックテンプレートを用意すると良いでしょう。
5-2: 学習の振り返りを仕組み化する方法
経験学習の効果を高めるには、偶発的な振り返りではなく、日常業務の中に「内省の時間」を意図的に組み込むことが重要です。
具体的な仕組み化の方法としては:
- 1on1で「経験→振り返り→次の行動」のフレームを定着させる
- プロジェクト終了後に「学びの共有会」や「リフレクションシート」を導入
- 月1回の“経験からの学び”を振り返る全社ワークショップの開催
このような取り組みにより、社員は「経験から学ぶ」という姿勢を習慣化できます。
ポイントは、振り返りを「当たり前の文化」にすること。評価制度やマネジメント方針に「経験学習」の視点を入れるのも有効です。
5-3: 研修や日報への組み込み方とツール活用例
経験学習を定着させるには、日々の業務や研修に無理なく組み込む工夫も大切です。
たとえば以下のような手法があります:
■ 研修での活用
- ロールプレイ後に「経験学習サイクル」に沿った記録を取らせる
- ワークショップで「振り返りジャーナル」を活用し、共有タイムを設ける
■ 日報・週報への活用
- 「今日一番の気づきは?」「なぜそう感じた?」「次はどうする?」といったフォーマットを日報に組み込む
- ChatGPTなどのAIツールを活用し、社員が書いた日報に対して内省を深める問いを自動提示
■ デジタルツールの活用例
- NotionやGoogleフォームで経験記録テンプレートを用意
- マイクロラーニングやLMSで「経験→内省→再チャレンジ」をトラッキング
- 経験学習特化型ツール(例:kokoroeなど)を導入し、習慣化を促す
こうしたツールを活用することで、経験学習のプロセスを見える化・仕組み化でき、忙しい現場でも自然と学びを促進することが可能になります。
次章では、実際に経験学習を導入した企業のリアルな成功事例を通じて、現場での実践イメージを具体的にご紹介します。
6: 成功企業の導入事例に学ぶ!経験学習のリアルな効果

経験学習の理論や手法について理解が深まっても、「実際に導入するとどうなるのか?」「現場で本当に効果があるのか?」といった点は、多くの人事・教育担当者にとって気になるところではないでしょうか。
この章では、実際に経験学習を導入した企業の事例をもとに、導入前後の変化や現場の反応、成功に導いた教育設計の工夫についてご紹介します。
6-1: 導入前後での変化と成果
あるIT企業では、若手社員の「研修で学んでも現場で活かせない」「受け身の姿勢が抜けない」といった課題が長年続いていました。そこで、経験学習サイクルを基盤としたOJT・社内研修プログラムを導入した結果、次のような変化が見られました。
■ 導入前の課題
- 座学中心で、知識の定着や応用が乏しい
- 上司からのフィードバックが属人的で一貫性がない
- 研修が一過性で終わり、業務に活かされていない
■ 導入後の成果
- 「体験→振り返り→次の行動」サイクルを組み込んだことで、主体的な学習態度が定着
- 日報や1on1を活用した内省の習慣化により、気づきが深まり行動が変化
- 経験を共有する文化が生まれ、チーム内での学びの連鎖が発生
結果として、若手の早期戦力化が進み、3年以内の離職率も大幅に改善されました。
6-2: 現場からの声と反応
実際に経験学習を取り入れた社員や管理職からは、以下のようなリアルな声が寄せられています。
若手社員の声
「ただやらされるのではなく、自分で考えて行動し、上司と振り返ることで成長を実感できるようになりました。」
「失敗しても“それも経験”として前向きに捉えられるようになり、挑戦するハードルが下がりました。」
管理職の声
「フィードバックの質が上がった。問いかけを通じて、部下の考えや成長プロセスがよく見えるようになった。」
「1on1が“報告の場”から“学びの場”へと変わったことで、チーム全体の雰囲気も良くなった。」
このように、経験学習の導入は、個人の学びだけでなくチーム全体の成長意欲や対話の質の向上にもつながっているのです。
6-3: 教育設計者の工夫と成功要因
経験学習の導入を成功させた企業では、教育設計にもいくつかの共通点があります。特に効果的だった工夫は以下の通りです。
■ フレーム化された問いの設計
毎回の1on1や研修で共通の問いを使うことで、上司によってバラつきが出ないように設計。「なぜそうしたのか?」「次はどうするか?」といった質問を習慣化しました。
■ 学びを記録・共有する仕組み
GoogleフォームやLMSを活用し、社員が経験学習の4ステップに沿って記録できるテンプレートを作成。学びの蓄積が可視化され、評価やキャリア支援にも活用できるようになりました。
■ マネジメント層の巻き込み
上層部や管理職が率先して経験学習を実践することで、現場への浸透がスムーズに進行。「やらせる教育」ではなく「共に学ぶ文化」へと変化しました。
これらの成功要因に共通するのは、単に経験学習を導入するのではなく、“仕組み化”と“文化づくり”の両面からアプローチしていることです。
次章では、ここまで紹介してきた経験学習のポイントを踏まえ、今後の人材育成にどう活かしていくべきかをまとめていきます。
7: まとめ|社員の成長を加速させるなら、経験学習が鍵になる

変化の激しいビジネス環境において、企業が持続的に成長していくためには、「自ら考え、行動できる人材」の育成が不可欠です。そうした人材を育てるカギとなるのが、**実践から学ぶ力を育てる「経験学習」**です。
経験学習は、単なる理論や知識の詰め込みではなく、「体験 → 振り返り → 学び → 実践」というサイクルを通じて、社員の行動変容と成長を促します。
OJTや研修、日常業務への組み込みによって、社員が日々の業務の中から学びを得る仕組みをつくることが、人事・教育部門に求められる役割です。
本記事では以下のポイントを解説しました:
- 経験学習の定義と基本概念、およびKolbモデルの4ステップ
- OJT・社内研修・フィードバックとの具体的な連携方法
- 経験学習による「自走人材」の育成と、学びの定着効果
- 成功企業の導入事例に見る、実際の成果と現場の反応
- 定着させるための問いの設計、仕組み化、ツール活用法
経験学習は特別な教育手法ではなく、企業文化や日常の業務の中に自然と組み込むことが可能な、再現性の高い育成手法です。
これからの人材育成をより実効性のあるものにするために、ぜひ経験学習の導入・強化を検討してみてはいかがでしょうか。
社員の成長が企業の成長を支える―そのための第一歩は、現場の“経験”を“学び”に変える仕組みづくりから始まります。
社員が現場で活かせる力を身につけるためには、ただ経験させるだけでなく、振り返りや反復による「経験学習」のサイクルをいかに習慣化できるかが鍵となります。
しかし、日々忙しい現場の中で、社員一人ひとりに適切なタイミングで学びを振り返らせ、定着を図るのは容易ではありません。
そこでおすすめしたいのが、**反復学習で記憶と知識を定着させるマイクロラーニングサービス「kokoroe」**です。
1日わずか5分のテスト形式で、学んだ知識を自然にアウトプットする習慣をつくり、経験を“確かな学び”へと変える仕組みを提供します。
自社独自のナレッジや業務知識もAIで簡単に問題化でき、教育の効果も数値で「見える化」。
「学んだのに忘れる」「伝えたのに伝わらない」といった教育の悩みを解決したい企業様に、kokoroeは最適な選択肢です。