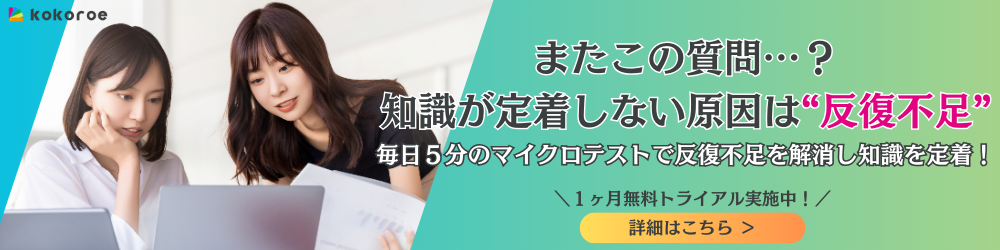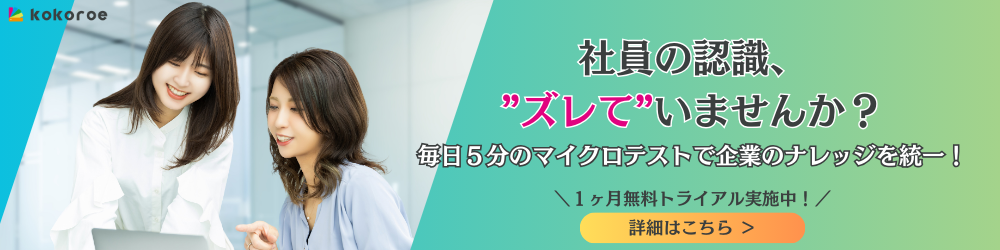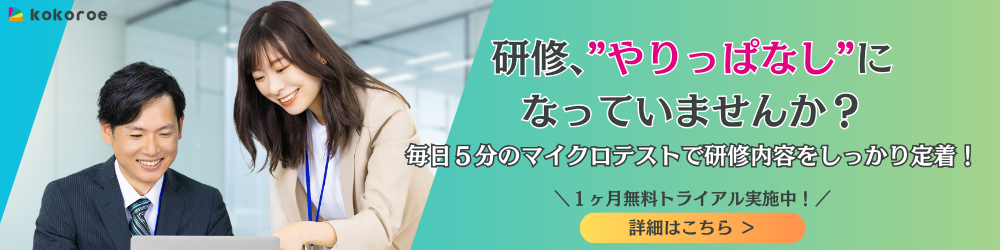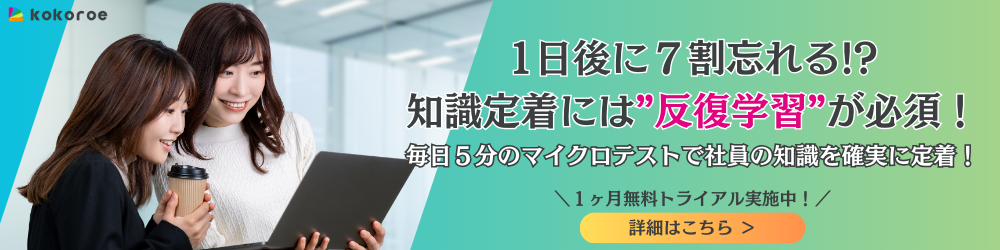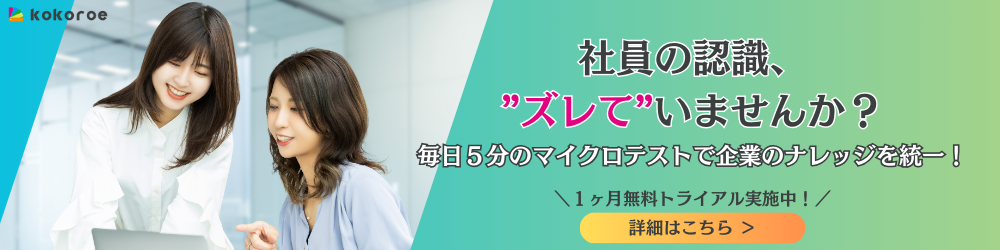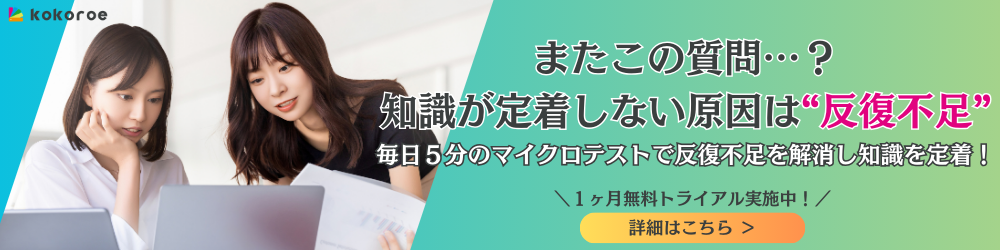「リテンション」とは?優秀な人材が辞めない会社の共通点を徹底解説!
人材の確保が難しくなる中で、注目を集めているのが「リテンション(人材定着)」です。優秀な人材を採用するだけでなく、長く活躍してもらうためには、職場環境や教育体制の見直しが欠かせません。本記事では、リテンションの基本から成功事例、具体的施策までをわかりやすく解説します。
1: リテンションとは?意味と注目される背景

近年、多くの企業が「人材の定着」に悩みを抱えており、その解決策として注目を集めているのが「リテンション」です。採用難の時代において、せっかく採用した優秀な人材が早期に離職してしまうのは、企業にとって大きな損失です。
本章では、そもそも「リテンション」とは何か、その注目の背景、そして現在の離職状況が企業に与える影響について詳しく解説していきます。
1-1: リテンションの基本的な意味とは
「リテンション(Retention)」とは、直訳すると「保持」「維持」という意味を持ち、ビジネスシーンにおいては従業員の定着や離職防止策を指します。人材リテンションは、「優秀な社員に長く働き続けてもらうための仕組みや戦略」を意味し、人事戦略の中でも重要度が増している分野です。
特に新卒・中途採用にかかるコストが年々高騰するなかで、採用した人材をいかに定着させ、戦力化し続けられるかが企業の競争力に直結する時代となっています。
1-2: なぜ今「リテンション」が注目されているのか
リテンションが急速に注目されるようになった背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。
- 人手不足の深刻化
少子高齢化や労働人口の減少により、多くの企業で人材の確保が困難になっています。そのため、「辞めさせないこと」がこれまで以上に重要になっています。 - 価値観の多様化とキャリア観の変化
従来の「長く勤めることが正義」という価値観は変わりつつあり、「自己成長」や「やりがい」を重視して転職を選ぶ若手社員も増加傾向にあります。 - 人的資本経営の浸透
社員一人ひとりの成長を企業の資産と捉える「人的資本経営」が広がり、リテンション施策が企業価値向上に直結するという考え方が一般化しつつあります。
こうした背景から、「採用重視」から「定着・育成重視」へと、企業の人材戦略がシフトしているのです。
1-3: 離職率の現状と企業への影響
厚生労働省のデータによると、日本における**新卒社員の3年以内の離職率は約30%**前後で推移しており、特に中小企業ではそれ以上の傾向も見られます。また、経験者採用においても、1年以内に離職するケースは決して少なくありません。
離職が企業に与える影響は非常に大きく、以下のような課題を引き起こします。
- 採用・教育コストの損失
- 組織の士気やチームワークの低下
- 業務の停滞による顧客対応や生産性への悪影響
- 企業ブランドへのマイナスイメージ
このようなリスクを防ぐためにも、リテンション施策を戦略的に設計・実行していくことが、今後の企業成長に不可欠です。
次の章では、優秀な人材が辞めない企業の共通点について、具体的な事例や特徴を交えて解説していきます。
2: 優秀な人材が辞めない会社の共通点とは?

リテンションを高めるには、優秀な人材が「この会社で働き続けたい」と思えるような職場環境と制度設計が欠かせません。実際に人材の定着率が高い企業には、いくつかの共通した特徴があります。
本章では、人事・教育担当者として注目すべき「辞めない会社」に共通する4つのポイントをご紹介します。
2-1: 組織へのエンゲージメントが高い
高いリテンションを実現している企業の多くは、社員の組織エンゲージメントが非常に強い傾向にあります。
エンゲージメントとは、社員が会社のビジョンや価値観に共感し、「この組織に貢献したい」と自発的に感じている状態を指します。
社員がエンゲージメントを持つことで、モチベーションが高まり、離職リスクも大幅に低下します。リテンション強化のためには、会社の理念やミッションを日々の業務に落とし込み、社員と共有する文化が必要です。
たとえば、定期的な社内報の配信、経営陣との対話会、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)浸透研修などが有効です。
2-2: 成長実感のある教育・研修制度がある
優秀な人材ほど、「自分がこの会社で成長できているかどうか」を重視します。そのため、成長実感のある教育・研修制度は、リテンション施策において極めて重要な要素です。
単発的な集合研修だけでなく、マイクロラーニング、OJT支援、定期的な振り返り面談などを通じて、成長を可視化し、実感させる仕組みがポイントとなります。
また、スキルアップだけでなく、自己理解を促すワークやフィードバック文化を育てる取り組みも、リテンション向上につながります。
2-3: キャリアパスの見える化と対話の仕組みがある
キャリアの先行きが不透明な職場では、社員が将来に不安を感じ、転職を選ぶ可能性が高まります。反対に、キャリアパスの見える化を行っている企業では、社員の安心感と定着率が高い傾向にあります。
役職や職種のステップアップ例を社内で公開したり、キャリア支援面談や社内公募制度を導入したりすることで、社員自身が「この会社でどう成長していけるのか」を明確に描けるようになります。
さらに、上司との1on1など、キャリアに関する対話の場を継続的に設けることも、リテンション施策として効果的です。
2-4: 心理的安全性と人間関係の良さを重視している
どれほど制度や待遇が整っていても、職場の人間関係が悪ければ、社員のリテンションは維持できません。近年では、心理的安全性が高い職場環境の重要性が強く認識されています。
心理的安全性とは、「自分の意見を自由に言える」「ミスをしても責められない」といった安心感がある状態を指します。
このような環境では、社員同士の信頼関係が深まり、離職率の低下につながります。
信頼関係の醸成には、上司による傾聴スキルの向上や、対話を重視するマネジメントが有効です。また、チームビルディングやワークショップの導入も、関係性を強化する手段として有効です。
このように、リテンションが高い企業には「人とのつながり」「成長の実感」「未来の見通し」といった**“働きがい”を生み出す要素**が共通しています。
次章では、これらの要素を実際の施策としてどう落とし込むかを解説していきます。
3: 人材リテンションを高めるための具体的施策

人材の定着率を高めるためには、理念やマインドだけでなく、具体的で再現性のある施策の実行が不可欠です。
本章では、企業の人事・教育担当者が今すぐ取り組める「リテンションを高めるための4つの具体策」について解説します。
3-1: 入社初期のオンボーディング強化
リテンションの第一歩は、「入社後のつまずきを防ぐこと」にあります。特に新入社員や中途入社社員は、入社直後の不安や孤独感から離職に繋がるケースも多く、オンボーディング施策の質が定着率を左右します。
効果的なオンボーディングには、以下のようなポイントが挙げられます。
- 初日からの明確な業務設計と目標設定
- 先輩社員によるメンター制度の導入
- 社内ルールや文化を理解できるオリエンテーション
- 入社後30日・60日・90日後の定期フォロー面談
「会社に受け入れられている」という実感を早い段階で持ってもらうことで、初期離職のリスクを大幅に低下させることができます。
3-2: 継続的なスキルアップ支援の導入
リテンション向上には、社員が自分の成長を実感し続けられる環境が欠かせません。そのためには、継続的なスキルアップ支援の仕組みが重要です。
たとえば、
- マイクロラーニング形式の学習コンテンツ提供
- eラーニングと実務を連動させたハイブリッド研修
- 社内ナレッジを活用した自社オリジナル教育の設計
- 資格取得や外部研修に対する支援制度
など、日々の業務と並行して学べる仕組みを整えることで、「この会社にいることで市場価値が高まっている」と社員が感じるようになり、リテンション効果が高まります。
3-3: 定期的な1on1やキャリア面談の実施
社員が会社に対して信頼感を持つためには、定期的なコミュニケーションとフィードバックの場が必要です。特に、上司や人事との1on1ミーティングやキャリア面談は、リテンション施策として非常に効果的です。
1on1の主な目的は、業務の進捗確認だけではありません。以下のような対話が重要です。
- 日々の悩みや不満のヒアリング
- キャリアの希望や不安の共有
- 組織や上司に対する信頼関係の構築
- 労働環境や業務負荷に関するチェック
社員一人ひとりの声に丁寧に耳を傾け、必要に応じて対応やフォローを行うことで、離職リスクを事前に察知しやすくなります。
3-4: 社員の声を拾う仕組みとフィードバック文化
人材リテンションを高めるには、「社員の声を拾い、組織を改善する文化づくり」が不可欠です。
せっかく1on1などで声を拾っても、それが組織改善につながらなければ、社員は「言ってもムダ」と感じてしまいます。
そのために有効なのが、
- 定期的なエンゲージメントサーベイの実施
- 社員アンケートの実施と結果共有
- ボトムアップの提案制度(社内ピッチやチャットボード)
- 意見を取り入れた施策の「見える化」と報告
このような取り組みにより、社員が「自分の意見が尊重されている」と感じ、心理的安全性とエンゲージメントが同時に高まる好循環が生まれます。
また、マネジメント層が率先して「感謝」や「称賛」を伝える文化を醸成することで、組織全体のコミュニケーションの質が向上し、結果としてリテンションにも大きく寄与します。
次章では、こうした施策によってリテンション向上に成功した具体的な企業事例をご紹介します。実践のヒントとしてぜひご活用ください。
4: リテンション施策を成功させた企業事例

リテンション向上の施策は理論だけでなく、「実際に効果が出た企業事例」から学ぶことが重要です。成功事例には、リテンションを高めるための具体的なヒントや実行のポイントが詰まっています。
ここでは、「社内教育」と「エンゲージメント」に焦点を当てた2つの企業事例を紹介します。
4-1: 社内教育の見直しで定着率を改善した事例
〈事例企業:IT系ベンチャー企業A社(従業員数:約150名)〉
A社は、成長著しいITベンチャー企業で、採用には成功していたものの、新卒社員の3年以内の離職率が50%以上という課題を抱えていました。ヒアリングの結果、離職理由の多くが「業務についていけない」「成長実感がない」といった“教育不足”に起因するものであると判明しました。
そこでA社は、以下のような社内教育の抜本的な見直しを行いました。
- 1日5分のマイクロラーニングで業務知識を反復習得
- OJTを補完するeラーニング+週次フィードバックの導入
- 自社のナレッジを可視化し、誰でも学べる環境を整備
- スキル定着を可視化する「理解度チェックテスト」の活用
これにより、社員一人ひとりの理解度や学習進捗が把握できるようになり、「自分が成長している」という実感が強まったことで、結果的に離職率が20%以下に改善されました。
人事担当者はこの事例から、リテンション向上には「研修内容の充実」だけでなく、「学習の継続性」と「可視化」が鍵であることを学ぶことができます。
4-2: エンゲージメント向上施策で離職を防いだ事例
〈事例企業:製造業B社(従業員数:約500名)〉
B社では、ミドル層社員のモチベーション低下と、それに伴う離職が課題となっていました。キャリアが中盤に差し掛かる30代〜40代の社員が、「今後のキャリアが見えない」「評価が不透明」と感じていたのです。
そこでB社は、社員エンゲージメントの向上に特化したリテンション施策を実行しました。
- 全社員を対象としたエンゲージメントサーベイを定期実施
- 回答結果をもとにチーム単位で課題を可視化し、対話の場を設置
- 管理職に対して「傾聴」「承認」「対話」を強化するマネジメント研修を実施
- キャリア面談の頻度を年1回から四半期ごとに変更し、未来の働き方を共有
これらの取り組みによって、社員の会社に対する信頼感が大きく向上し、離職率は30%→15%に半減。特にミドル層の離職が大幅に改善されました。
この事例は、人材のリテンションを高めるには「エンゲージメントの状態を把握し、個々にアプローチする」ことの重要性を示しています。
このように、リテンション施策は業種・規模を問わず効果を発揮しますが、成功の鍵は「自社の課題に応じた的確な打ち手を選ぶこと」です。
次章では、リテンション向上のために人事・教育担当者が今すぐ実行できる具体的ステップを解説していきます。
5: リテンション向上のために人事・教育担当者が今すぐできること

リテンション施策というと「全社的な改革」や「大規模な制度導入」をイメージしがちですが、実は小さな一歩の積み重ねが最も重要です。
ここでは、企業の人事・教育担当者がすぐに着手できる、リテンション向上のための実践ステップを3つに分けて紹介します。
5-1: 自社の離職要因を正しく分析する
まず重要なのは、「なぜ社員が辞めているのか」を正確に把握することです。リテンションを高めるには、現状の課題を明確にすることが出発点となります。
有効な手法には以下のようなものがあります。
- 退職者インタビューやアンケートの実施
- 定期的なエンゲージメントサーベイ
- 各部署ごとの離職率・傾向のデータ分析
- 面談時の不満・悩みの記録の整理と可視化
特に、「上司との関係性」「キャリアの見通し」「職場の雰囲気」といった定性的な要因も拾い上げることがポイントです。
原因を把握せずに対策を打っても、的外れになりかねません。現場の声に耳を傾け、離職の背景を「見える化」することから始めましょう。
5-2: 施策を小さく始め、PDCAを回す
リテンション施策においては、一度にすべてを変えようとせず、スモールスタートで取り組むことが成功の鍵です。
たとえば、
- 一部の部署で1on1面談を試験導入
- 新入社員向けにマイクロテストを数週間導入
- 教育研修の一部をeラーニング化
- エンゲージメントサーベイの設問数を減らして簡易実施
このように**「小さく始めて、効果を確認しながら改善する」**ことで、現場の負担を減らしながら、持続的なリテンション施策を進めることができます。
特に人事や教育部門は、業務と並行して多くのことを担っているため、PDCAを意識した段階的なアプローチが現実的です。
5-3: 教育×データ活用で人材定着を可視化する
リテンション施策は「感覚」ではなく、「データ」に基づく運用が成功のカギを握ります。中でも、教育施策とデータ分析の連携は非常に効果的です。
たとえば、
- 学習コンテンツの受講率と理解度の可視化
- マイクロテストの定着スコアを時系列で管理
- 研修後のアンケートと離職率の相関を分析
- スキル進捗と人事評価・定着率のデータ連携
こうした可視化により、「この教育施策がリテンションにどう効いているのか」を客観的に判断できるようになります。
さらに、AIやLMS(学習管理システム)を活用すれば、個々の学習傾向に合わせた最適なフォローアップも実現可能です。
“学びを見える化する”ことが、リテンションの質的向上にもつながります。
次章では、リテンションの重要性をあらためて整理しながら、「今後どのような視点で取り組んでいくべきか」についてまとめていきます。
6: まとめ|人材リテンションは「会社の魅力」の最前線

これまで見てきたように、「リテンション(人材定着)」は単なる離職防止の施策ではなく、企業の魅力そのものを映し出す鏡ともいえます。
採用活動がますます困難になるなかで、「人材をいかに引き止めるか」ではなく、「この会社で働き続けたいと思わせる環境をどうつくるか」が問われています。
それは、人事や教育担当者が担うべき、極めて戦略的かつ価値の高い領域です。
6-1: リテンション対策の鍵は“個別最適化”と“継続性”
リテンション向上を成功させている企業に共通するのは、「すべての社員に同じ施策を当てはめない」という姿勢です。
**社員一人ひとりの価値観・キャリア・課題に応じた“個別最適化”**が重要になります。
たとえば、新卒と中途では求めるサポートが異なり、若手とミドル層ではキャリアへの期待も変わってきます。だからこそ、画一的な制度ではなく、「誰に、どんな支援が必要か」を見極める設計が求められます。
さらに、リテンション施策は一度やって終わりではなく、継続的に見直し・改善していくことが成功のカギです。定期的なデータ分析や現場の声の収集を通じて、柔軟に対応していく体制づくりが求められます。
6-2: 自社に合ったリテンション戦略を見つけよう
リテンション対策に「絶対的な正解」はありません。業種、企業規模、社風、社員構成などによって、最適なアプローチは異なります。
大切なのは、他社の事例を参考にしながらも、自社の課題に合ったリテンション戦略をカスタマイズしていくことです。
たとえば、ある企業ではマイクロテストによる知識定着が効果を発揮し、別の企業ではエンゲージメントサーベイとキャリア支援面談の組み合わせが成功しています。
まずは小さな一歩からでもかまいません。今の課題を正しく把握し、「社員が辞めない理由」をつくり続けることで、企業の成長と社員の満足度が両立する理想の組織が形づくられていくでしょう。
リテンションは、採用以上に“企業の未来”を左右するテーマです。人事・教育担当者の皆様こそが、その未来をつくるキープレイヤーです。
明日からの一歩が、組織の強さを大きく変えていきます。
人材の定着には、エンゲージメント向上やキャリア支援だけでなく、「知識の定着」も不可欠です。いくら教育しても学んだ内容が忘れられてしまえば、成長実感もパフォーマンスも得られず、リテンションの低下につながります。
この課題を解決するのが、**毎日5分の反復学習で知識を定着させる教育サービス『kokoroe』**です。
「企業ごとに異なる教育内容」を簡単にテスト化し、社員の理解度や習熟度をデータで可視化。学びの継続を促しながら、“伝えたつもり”や“学んだつもり”をなくす仕組みを提供します。
社員教育の成果をしっかりリテンションにつなげたいとお考えの方は、ぜひ一度『kokoroe』をご活用ください。